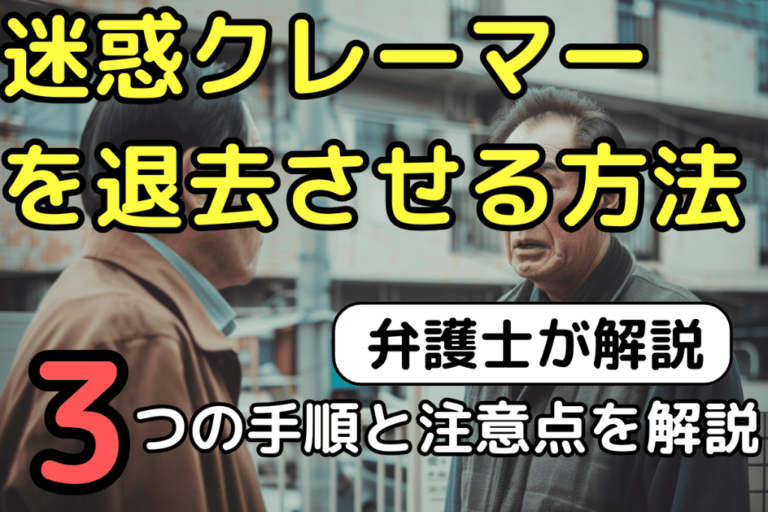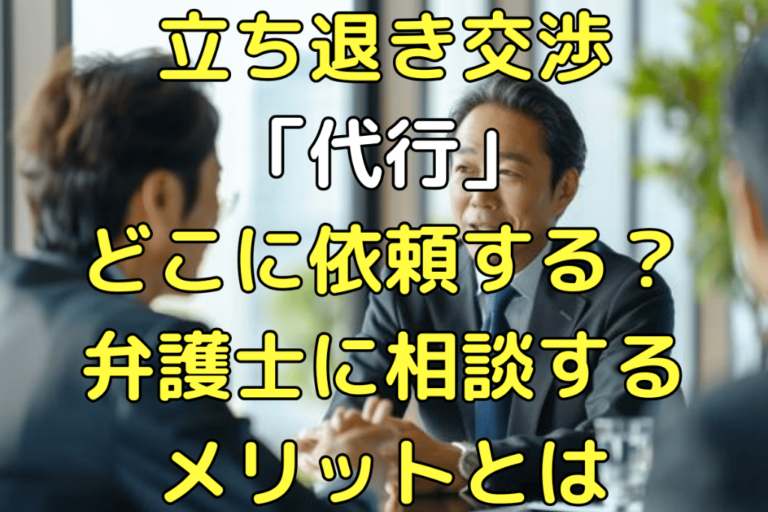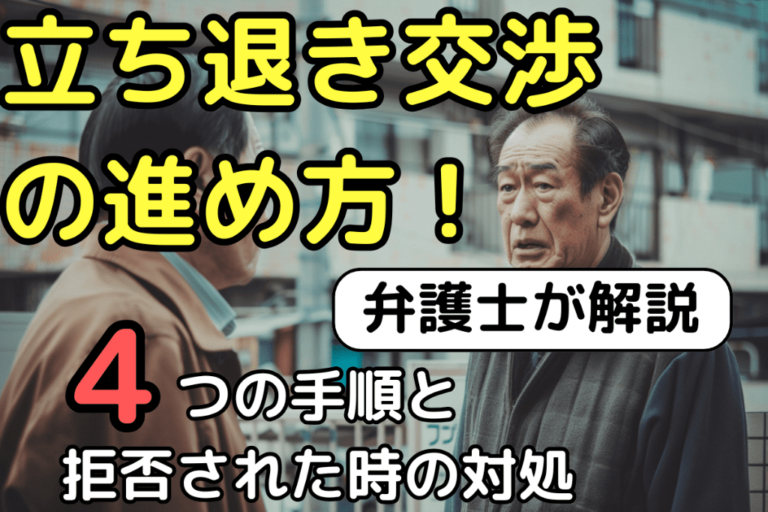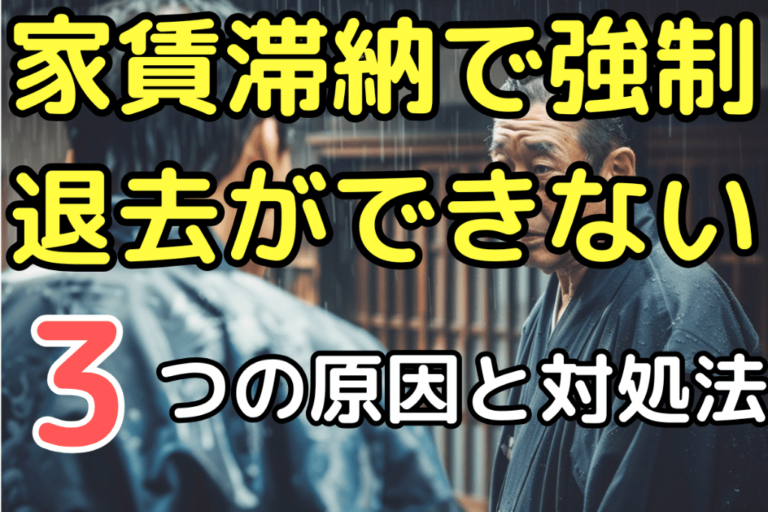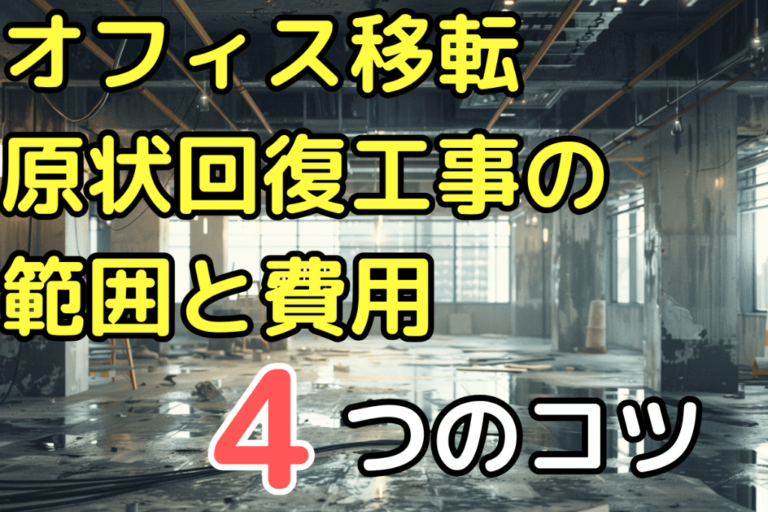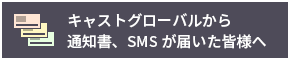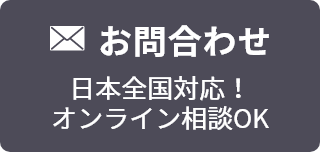- 最終更新:
使用貸借の立ち退き|立ち退き料相場と拒否された場合の対処法を解説
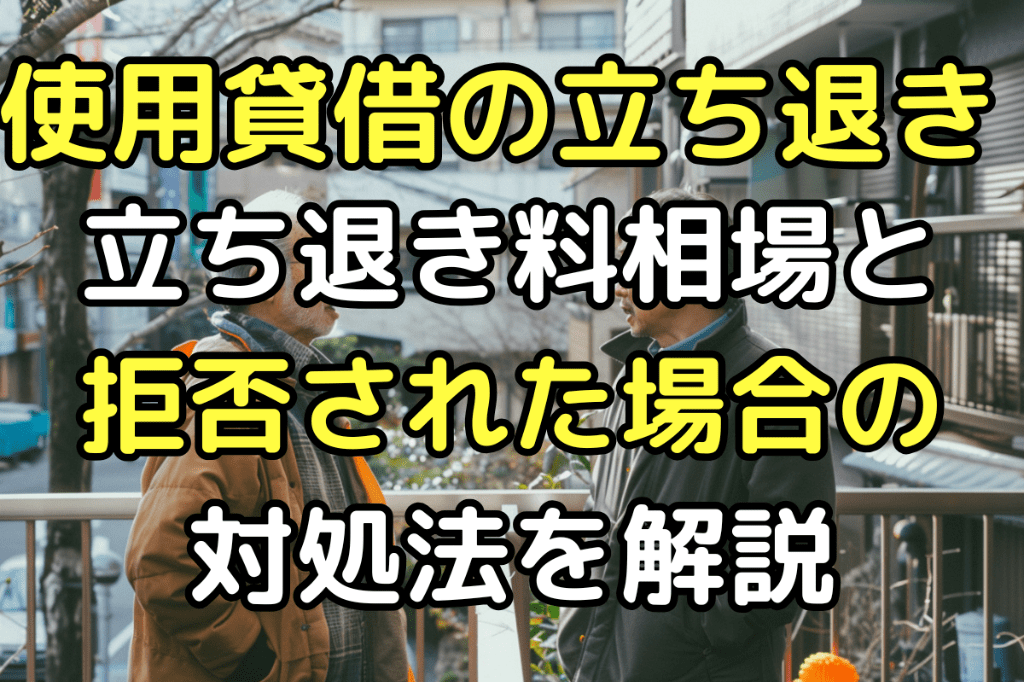
信頼関係があったので無料で家を貸してあげたけど、その家を使うことになった、または信頼関係がなくなったから出ていってほしい。
使用貸借で貸したのだから、すんなり出ていって欲しいですよね。
本記事では、使用貸借とは何か、使用貸借での立ち退きできる場合、出来ない場合、正当事由と立ち退き料は必要か、スムーズに立ち退いてもらう方法を解説します。
【この記事でわかること】
- 使用貸借とは、土地や建物など不動産や動産を無償で貸し借りする契約であること
- 使用貸借で問題となるケースは、不動産を長期間に渡って貸し相続が発生した場合であること
- 使用貸借では貸主の都合で立ち退いてもらえるのが基本であること
- 期間と目的を定めて貸した場合はその期間、その目的達成まで立ち退いてもらえないこと
- 使用貸借の立ち退きに。正当事由と立ち退き料は不要であること
- 場合によっては引越し費用を払うこともあり
- 立ち退き裁判をする流れ
- 弁護士に相談するタイミングとメリット
なお、立ち退き交渉のコツについて知りたい方は、「オーナー必見!築40年アパート立ち退き交渉のコツと立ち退き料相場」をご覧ください。
目次
1.使用貸借とは?基礎知識とルール
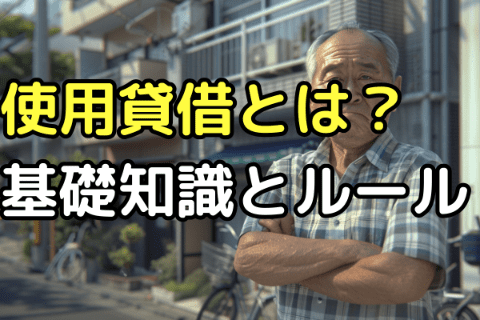
「使用貸借」という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、実は身近にあふれています。
使用貸借とは、土地や建物など不動産や動産を無償で貸し借りする契約のことです(民法593条)。
たとえば親が所有する家に子がタダで住む、友達から時計を借りて少しの間つけさせえてもらう場合など、無料で貸すケースが該当します。
主に、当事者間の信頼関係を前提にして、ちょっと貸してあげるという場合に使われます。賃貸借との違いは、無料だということです。
なお、無料でなかったとしても、使用貸借と認められる場合があります。
つまり、ここでいう無料とは賃料の対価といえるような支払いがあるかということです。
例えば、水道光熱費などの必要経費で1万円もらっていたという場合は、使用貸借であるといえます。
1)使用貸借で問題となる主なケース
使用貸借は身近に溢れていて、通常はありがとうといって返して終わるので、問題となりません。
ですが、次の3つがあると問題が起きやすいです。
- 家などの不動産
- 長期間に渡って貸す
- 相続が発生する
例えば、親戚の土地を借りて家を建てていて、地代は払っていなかった(固定資産税程度は払っていた)ところ、その親戚が亡くなり、相続人から立ち退いて欲しいと連絡がくるなどです。
親戚ならまだ遠い血縁ですが、兄弟や親子でも起きています。
兄弟、親の土地を借りていたが、兄弟、親が亡くなり、自分の兄弟から出て行けと言われる場合です。
2)契約書がなくても使用貸借は成立する
使用貸借は、契約書がなくても法的には「契約」として成立しています。
一般的に使用貸借契約書がないことの方が多いでしょう。
子どもにタダで家を貸してあげるというときに契約書を作るという文化は一般的ではありません。
こういったケースで「あの家(無償で)貸すから住んでいいよ」という口約束でも、立派な契約ということです。
ですが、無料の貸し借りで、口約束だからこそトラブルになるケースはあります。
家などの重要な財産で後々争いが起きかねない場合は、今からでも「使用貸借契約書」を作る方が望ましいです。
2.使用貸借は貸主の都合で立ち退きさせられるのが基本!
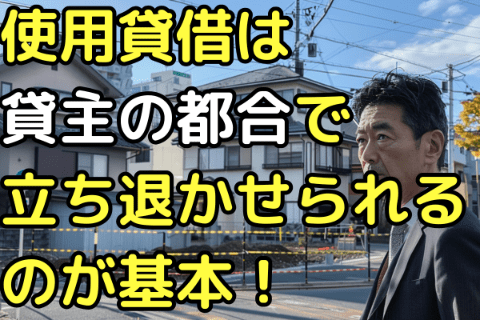
では、使用貸借の立ち退きに話を移しましょう。
結論、使用貸借の立ち退き事案において、貸主都合でいつでも立ち退きを求めることができるケースが大半です。
ご相談いただくケースで多いのが、使用貸借で貸していた土地や家が「相続」で受け継がれたケースです。
親が信頼関係を基礎に無償で使わせてあげていたが、親が亡くなり、不動産を処分したいから出て行って欲しいというものです。
このようなケースでは原則、立ち退いてもらうことができます。
ただし、厳密には必ずしも貸主都合で立ち退かせられるわけではなく、以下の3つが条件になります。
- 口頭で貸す約束はしたがまだ不動産を引き渡していない場合(民法593の2条)
- 使用する目的と期間を定めない場合(民法598条2項)
- 使用する目的を決めたが期間を定めずにいて、目的を達成する期間を経過したとき(民法598条1項)
要するに、土地や建物を貸すときに(ⅰ)期間を定めていた場合、(ⅱ)目的を定めていた場合は、それを達成するまで立ち退きを拒否される余地があるということです。
1)例外①使用貸借の「期間」を定めていた場合
使用貸借の借主が立ち退きを拒否できる例外的なケースの1つ目は、「期間」を定めていた場合です。
例えば、「3年この家に住んでいいよ」などという約束だった場合、1年や2年で貸主側から一方的に立ち退きを求めることはできません。
口約束であっても、3年という期間も含めて「契約内容」だからです。
借主としては、約束してもらった以上、その期間中はその土地なり建物なりを利用する権利があるということです。
もっとも、期間を約束したことを借主が証明しなければならず、契約書がなかった場合は証明が困難です。
したがって、出ていってもらえる可能があります。
2)例外②使用の「目的」を定めていた場合
2つ目は、借主の「目的」を定めた上で貸していたケースです。
例えば、友人が海外から帰任して、日本で住居を借りるまでの間、無償で家を使わせてあげる場合や、新居を建設中でできるまでの間無償で家を使わせてあげる場合です。
この場合も、「日本で住居を借りるまで」「新居の建設が終わるまで」といった目的も含めて契約内容ですから、達成できる合理的期間を待たないといけません。
とはいえ、期間や目的が果たされていないケースでも、話し合いできちんと合意できれば立ち退いてもらうことはできます。
そのためにも、使用貸借での立ち退きは円満な話し合い・交渉が必須です(円満交渉のポイントは4章で解説)。
3.使用貸借の立ち退きに「正当事由」と「立ち退き料」は必要?
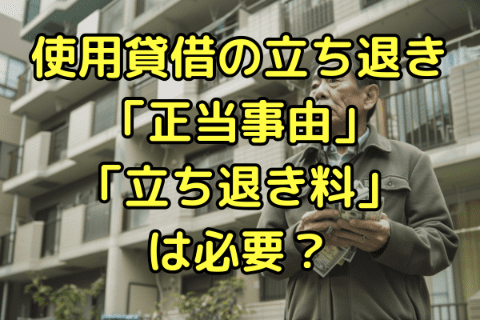
賃貸借について知識がある方であれば、立ち退きを求める際は「正当事由」と「立ち退き料」が必要だと聞いたことがあるのではないでしょうか。
使用貸借ならどうかといえば、結論、どちらも必要ありません。
その根拠に加え、一部例外もあるので、以下で詳しく述べます。
1)正当事由は必要ない
使用貸借では、立ち退いてもらうのに「正当事由」は必要ありません。
正当事由は、借地借家法の定めによるものですが、土地建物を住居目的で有償で借している場合で契約を更新せず終了させる場合に必要な要件です。
ですから、使用貸借であれば、正当事由は必要ないということになります。
2)法的には立ち退き料も必要ない
法的には、使用貸借において立ち退き料は払う必要がありません。
立ち退き料は、正当事由の補完であり、借地借家法(旧借地法)の保護がある場合をいいます。
使用貸借はその保護がありません。
ですが、立ち退き料は、立ち退いてもらうために払う費用という場合にも使われます。
その意味での立ち退き料は、払うことを検討してもいいでしょう。
法律上は立ち退かせることができるとしても、次章で解説しますが、裁判・強制執行となると費用と時間がかかります。
であれば、引っ越し代くらい払ってあげて出て行ってくれるなら、あなたにとっても都合がよいのではないでしょうか。
4.使用貸借の立ち退きを円満に進める3つの交渉術
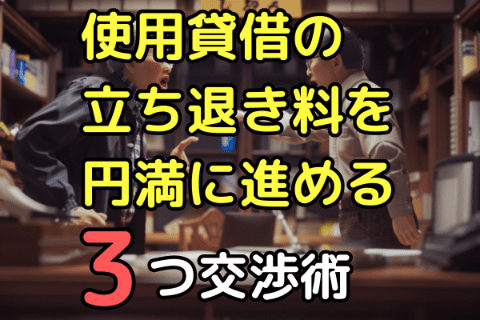
法律上、借主に出て行ってもらうことができるからといって、借主がすんなり出て行ってくれるとは限りません。
ですが、使用貸借は主に親子や親戚などの関係で交わされることが多く、人間関係の悪化は避けたいところでしょう。
そこで、以下に述べるポイントをおさえて、借主と円満に立ち退きを決められるよう相談してみてください。
1)立ち退いてほしい理由・事情を丁寧に説明する
先述のように、使用貸借は無料で貸してあげているのであり、借主は出て行くのが当然です。
ですが、「出て行って当然だ」という言い方をしてしまうと、借主がへそを曲げてしまい、問題解決が遠のきます。
その不動産はこちらが利用しなくてはいけない状況になったから、立ち退いて欲しいということをお願いするように伝えましょう。
法律上出て行かなくてはなりませんということは、最初に伝えない方がいいでしょう。
「一生涯使っていいと言ったじゃないか」など無用な争点が生まれてしまいます。
ゴールは、借主がこれまでありがとうございましたとお礼を言いながら、自主的に出て行ってくれることです。
2)立ち退きを拒否されたら「法的根拠」の説明
やむなく出て行ってもらいたい旨を紳士的、丁寧に伝えたにもかかわらず、拒否された場合は、法律上、拒否することはできないことをしっかり伝えます。
法的なルールと根拠は2章で述べた通り。「期間」か「目的」が定められていない場合は、貸主の都合でいつでも立ち退いてもらえることになっています。
また、使用貸借契約を解除する旨の通知を内容証明で送ると良いでしょう。
3)引っ越し費用などを負担してあげる
本来は引っ越し費用を含めた立ち退いてもらうための費用を払う必要はありません。
ですが、次章で解説しますが、法律上立ち退かせることができるとしても、それを訴訟、強制執行で実現するには時間とお金がかかります。
そうであれば、引っ越し代くらいで出て行ってくれるなら安いものというケースがあります。
引っ越し代を払うことを条件に立ち退いてもらうように交渉しましょう。
5.使用貸借で立ち退き拒否された場合の裁判・強制執行
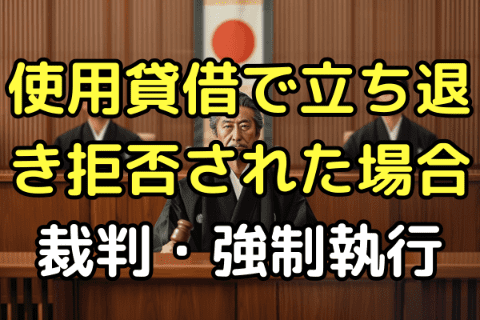
使用貸借ではなく賃貸借であると主張する場合など相手が立ち退かない場合は、立ち退きを求める裁判・強制執行を検討します。
【裁判・強制執行の流れ】
- 仮処分の検討
- 訴状の提出
- 期日(審理)の開始
- 判決
- 強制執行申し立て
- 明け渡しの断行
裁判の前に仮処分の検討も必要です。
無料で借りているにもかかわらずごねて出て行かないという借主は、倫理的な行動をとらない人である可能性があります。
そうすると、裁判で勝利しても、借主が別の人に明け渡してしまっていたなんてこともあります。
その場合は、その借主に対する勝訴判決は使えないからです。
裁判費用は、裁判所に払う費用が5万円程度、強制執行を補助してくれる業者に払う費用が30万円程度、弁護士費用で100万円程度です。
ご自分ですべてするとしても、費用は大きな負担になります。
さらに詳しく期間、費用、流れを詳しく知りたい方は、「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」をご覧ください。
6.使用貸借契約での立ち退きに関する重要判例
1)貸主側が勝訴した具体的判例
東京地方裁判所(令和5年11月15日)
事案の概要:
亡Aが、借主に対して、ここに無償で住んでほしいとビルの1室を貸した。
借主は一生涯住んでも良いといわれているし、Aが亡くなったことで出て行けというのは権利濫用だと反論した。
結果:
Aが亡くなって退去を求められたにもかかわらず、それから5年もの間無償で住み続けており、十分な退去時間を与えられたこと、Xは非正規雇用とはいえ収入があることから引っ越し費用は捻出できるとして、権利濫用ではないとした。
したがって、貸主が勝訴し立ち退きが認められた。
2)貸主側が敗訴した具体的判例
東京地方裁判所(令和5年7月5日)
事案の概要:
亡Aは、アパートを建て借主が一部無償で住み、残りは第三者に賃貸していた。
Aが死亡しBが相続した後は、Bは残ローンを相続するも、借主が、賃料の管理、そこからローンの支払いをしてきた。
Bが死亡してCが相続し、借主に立ち退きを求めた。
結果:
これらの事情を考慮すると、本件使用貸借は、被告を扶養しその生活を保障することを目的として締結されたと認められる。
被告は、85歳で賃料収入から得られる収入以外に収入がなく、他に住むところがない。
借主が建物を使用する必要がないとはいえない。
よって、本件使用貸借の目的に従った使用が終了していると認められない。
したがって、貸主が敗訴し立ち退きが認められなかった。
7.弁護士に相談するタイミングと3つのメリット
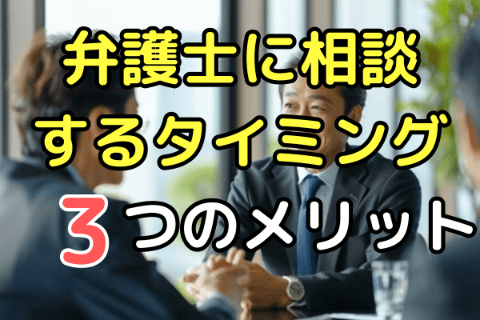
問題が複雑になる前に弁護士に相談、依頼することを検討ください。
弁護士に相談するタイミングは、紳士的、丁寧に出て行ってほしい旨を伝えたのに、出て行くことを前提とした話し合いにならなかった時点です。
この状況は、もうあと一つ何か起きれば問題が複雑になってしまいます。
弁護士に依頼すると次の3つのメリットがあります。
1)速やかな立ち退きを実現できる
借主に早く出て行ってもらってその不動産を利用することが大切です。
立ち退きに強い弁護士に依頼することで、交渉から訴状の提出、強制執行まで迅速かつ正確な対応が可能です。
出来る限りはやく出て行ってもらって問題を解決することが期待できます。
2)裁判外の解決も見込める
裁判までせずに、話し合いによって解決できる可能性が上がります。
裁判による解決は時間、費用が掛かるため、避けたい解決方法です。
立ち退きに強い弁護士に依頼することで、借主と冷静に話し合い、あらゆるカードを使いながら適切かつ柔軟な解決を図れます。
弁護士の立場からしても裁判外による早期解決が理想的解決です。
3)交渉から明け渡しまでまるっと任せられる
使用貸借ですんなり出て行ってくれないとなると、借主との交渉、立ち退き交渉から明け渡し完了までの対応は困難が予想されます。
立ち退きに強い弁護士に依頼することで、これら一連の流れをまるっと任せることが出来ます。
困難な対応を弁護士に任せられて、借主との交渉もする必要がなくなり、多大なストレスから解放されます。
まとめ
使用貸借の立ち退きについて、まとめていきます。
使用貸借とは、不動産や動産を無償で貸し借りする契約のことで、家族間や親戚間など身近でよく発生します。
無料で貸すことが原則ですが、必要経費の支払い程度なら使用貸借と認められる場合があります。
契約書がなくても口約束だけで契約は成立しますが、後のトラブル防止のために契約書を作成する方が望ましいです。
使用貸借では、貸主がいつでも立ち退きを求めることができるのが基本です。
ただし、①期間が明確に定められている場合や、②使用目的(例:新居建設中の一時的な利用)がある場合は、期間や目的が満たされるまで立ち退きを拒否されることがあります。
賃貸借とは異なり、使用貸借には立ち退きに際しての「正当事由」や「立ち退き料」は法律上必要ありません。
ですが、円満に進めるために引っ越し費用等を提供することがあります。
立ち退きを円滑に進めるためには、事情を丁寧に説明し、法的根拠を明示した上で、相手の状況を考慮した交渉を行うことが重要です。
立ち退きを拒否された場合、裁判や強制執行を検討することになりますが、時間と費用がかかるため、紛争が深刻化する前に弁護士に相談することを推奨します。
専門家である弁護士に依頼することで迅速な対応、裁判外の解決、交渉から明け渡しまで一括対応できるなど、多くのメリットがあります。
スムーズに立ち退きが進むように本記事が参考になれば幸いです。



 地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約
地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約