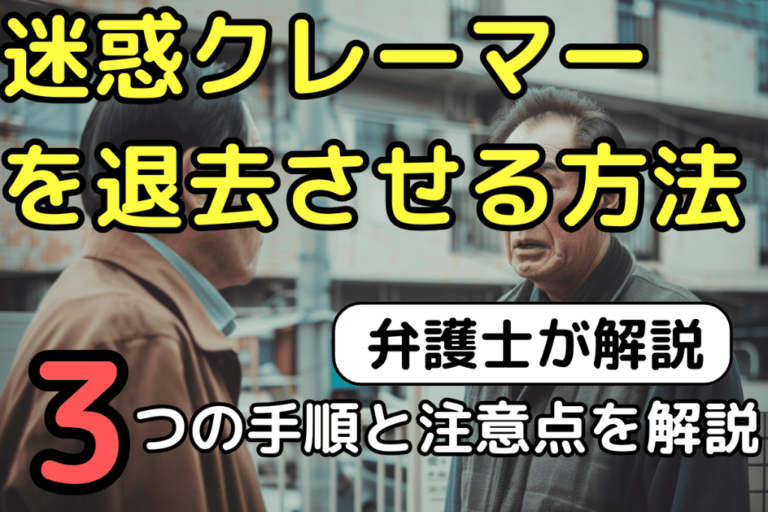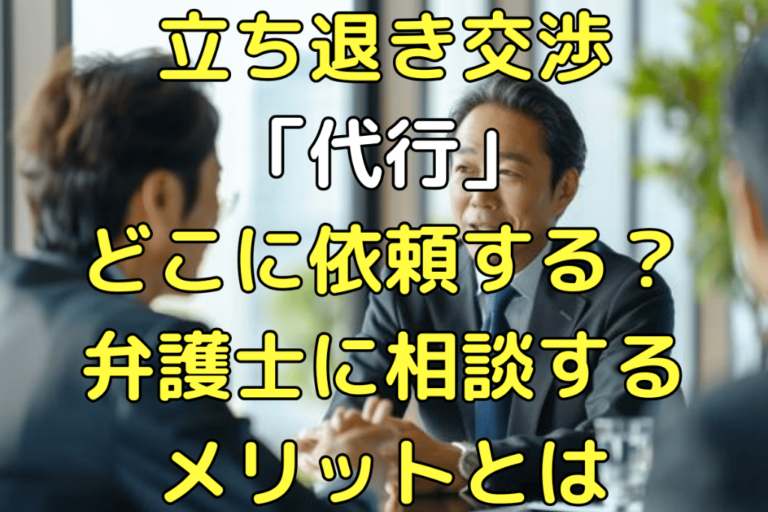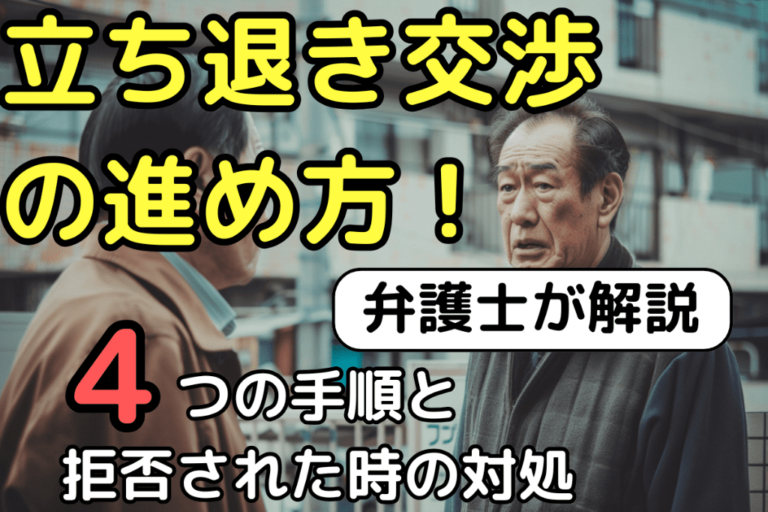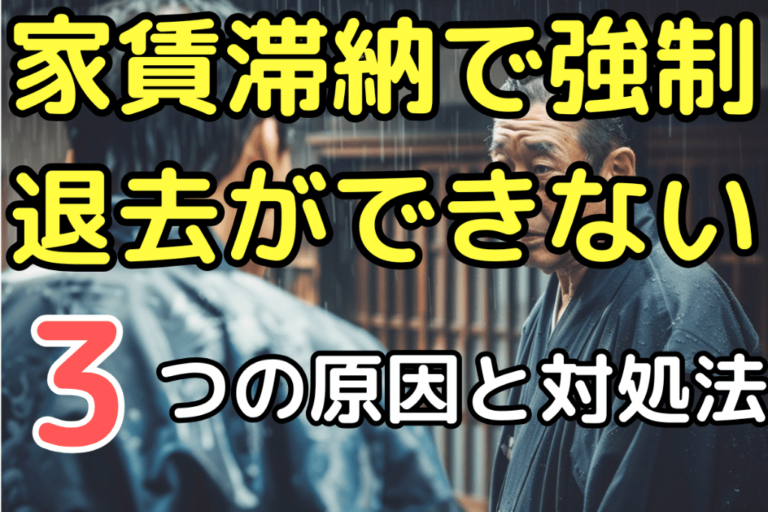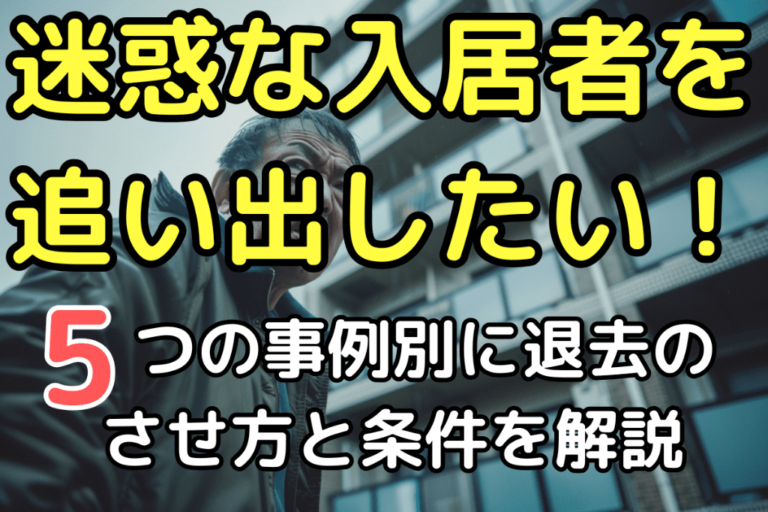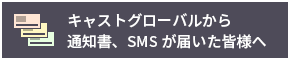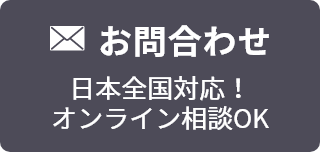- 最終更新:
オフィス移転の原状回復工事の範囲と費用を抑える4つのコツを解説!
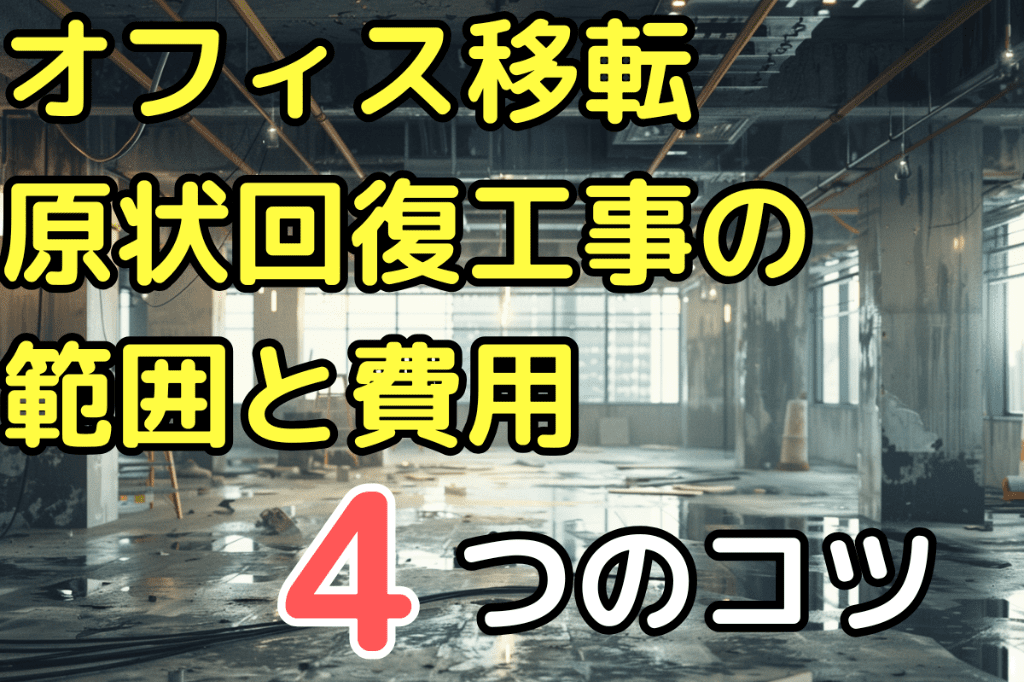
オフィス移転の際に高額な原状回復費用を請求されてお困りでしょう。
結論、オフィス退去時の高額な原状回復費用は、減額できる可能性が十分にあります。
ですが、賃貸借契約書の内容、原状回復工事の内容によって、大きく異なります。
そこで、本記事では法人担当者様向けに、費用相場の具体例、請求の適正化方法、実践的な交渉術を専門家が詳しく解説します。
【この記事でわかること】
- オフィスの原状回復工事費用は減額できること
- 原状回復とは、賃借人の故意過失による損耗を回復させること
- 契約内容によっては、原状回復の範囲は異なること
- 建物の躯体に関わるかによって業者の選定と費用負担者が変わること
- スケルトン、居抜き、セットアップオフィス別の原状回復範囲
- オフィスの原状回復工事費用が高額になるのは
- 業者指定で価格競争が働かないこと
- アップグレードしている可能性があること
- 原状回復の範囲が広いこと
- 原状回復工事費用を削減する4つのポイント
- 原状回復の範囲が適切か
- 経年劣化・通常損耗であるのか
- アップグレードしていないか
- 各項目の工事費用が適切か
- 弁護士に任せることで、4つのポイントを整理でき、減額幅が大きくなる可能性があること
- 次の物件で原状回復費用を抑えるポイント
なお、賃貸住宅の原状回復費用ついて知りたい方は、「大家都合の退去の原状回復費用はどうなる?免除にする交渉方法を解説」をご覧ください。
目次
1. 【前提】オフィスの原状回復費用は減額できる
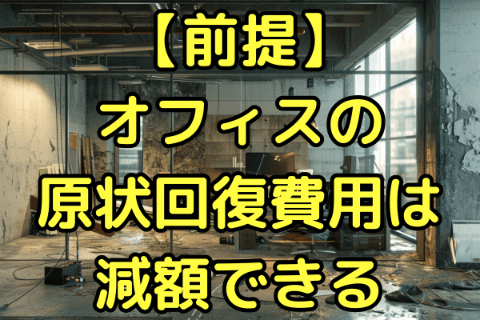
結論ですが、オフィスの原状回復工事費用を減額することはほとんどの場合できます。
原状回復工事の内容は、大家さん側が決めて費用を見積もりしてきます。
この時、”妥当な”金額よりも高く請求してくるケースが多いからです。
大家さんとしては次のテナントのため、自分の資産価値を維持するため、出来る限りの工事をしてもらいたいです。
悪意があるわけではないでしょうけれど、適正な見積もりが出てくるというのは期待できません。
2. オフィスの『原状回復』とは何か?その範囲
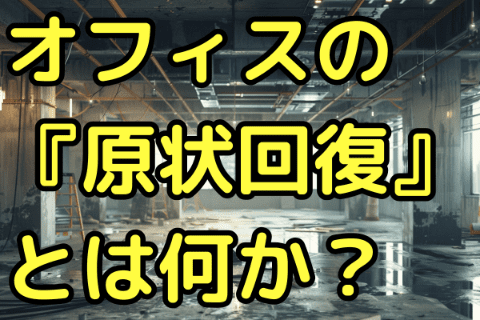
原状回復とは、賃借人の故意・過失による損耗・毀損を復旧することです。
原状(借りたときの状態)に戻す(回復させる)ということではありません。
つまり、経年劣化、自然損耗による部分は原則として大家さんが負担するものとなります(民法621条)。
ですが、この規定は絶対に守らないといけないわけではありません。
賃貸借契約を締結するときに、原状回復をどこまでしなければならないのかということを定めることができます。
原状回復工事についてのポイントは3つになります。
- 賃貸借契約で原状回復の範囲
- 原状回復工事の内容が適切か
- 原状回復工事の費用が適切か
では、原状回復の範囲を確認するにあたり、原状回復の区分と費用負担者について解説します。
1)オフィスの原状回復工事の区分と費用負担者
オフィスにおける原状回復工事は、次の区分があり費用負担は次のとおりです。
| 項目 | A工事 | B工事 | C工事 |
| 対象範囲 | 【建物の躯体、共有部分】
● 建物の外装・外壁 ● 共用トイレ ● 消防設備 ● エレベーターホール |
【専有部分で建物躯体に影響を及ぼすもの】
● 空調設備 ● 防災設備 ● 防水設備 など |
【専有部分のうち建物躯体に影響を及ぼさないもの】
● コンセント、照明の設置、増設 ● 建具、家具の設置 ● クロス、床のタイルやカーペット |
| 業者選定者 | オーナー | オーナー | テナント |
| 発注者 | オーナー | テナント | テナント |
| 費用負担者 | オーナー | テナント | テナント |
A工事とは、建物の躯体、共有部分に関わる工事をいい、B工事とは、専有部分で建物躯体に影響を及ぼすもの、C工事とは、専有部分のうち建物躯体に影響を及ぼさないものをいいます。
A工事は比較的区別しやすいのですが、B工事とC工事の区別はオーナーの考えによって異なります。
費用負担は、いずれであってもこちら側ではありますが、業者選定がこちらでできないというのが大きな違いです。
これらはあくまで一般的にということであり、個別には異なる可能性があることをご理解ください。
2)契約書の記載は不明確なことが多い!
賃貸借契約書に原状回復とはどういう原状に戻すのかが書いてあると述べました。
ですが、原状回復についての記載は、驚くほど簡素でどういう条件が現状であるかが明らかな契約書を見たことがありません。
つまり逆にいうと、値下げを争える余地が十分にあるということです。
3. オフィスの原状回復の対象範囲を3つのケース別に解説
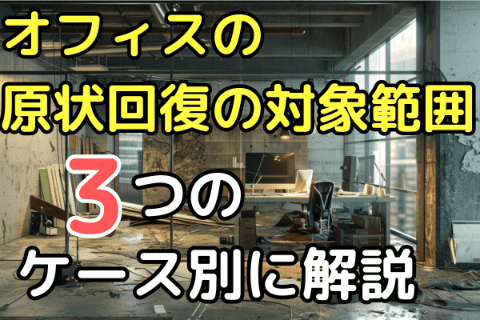
再度ですが、原則論をお伝えします。
経年劣化、自然損耗による部分は原則として大家さんが負担するものとなります(民法621条)。
つまり本来、賃借人が負担するべきは故意・過失で損耗した部分を修理するだけです。
ですが、契約によってこれは修正することが可能であり、オフィス賃貸は、多くの場合、賃借人の修繕義務の範囲が大きくなっています。
賃貸借契約書に原状に戻すとはどういう状態に戻すのかが記載されているということです。
1)スケルトンの場合
借りた際にスケルトン(建物の柱や梁、床など構造躯体のみの状況)である場合の原状回復工事です。
この場合は、戻す状況が比較的わかりやすく、ほぼすべてを撤去して、同様の状況に戻すことになります。
ですが、これに加えて、壁の塗装、天井の塗装、床仕上材の張替えをするという内容になっていることもあります。
つまり、壁や床の塗装、床仕上材に関して、自然損耗も修繕することになります。
2)居抜きで借りた場合
前賃借人の造作物をそのまま譲り受け借りた場合の原状回復工事です。
この場合は、前賃借人が借りた際の状況に戻すという契約になっているでしょう。
注意点は、自分が借りた状態とは異なるため、どのような状態であったかを確認することはできないことです。
造作が不要になったことで初期費用が大幅に削減できることに目が行きがちですが、前賃借人から状況を引き継いでおくことが望ましいです。
3)セットアップオフィス
昨今東京都心部を中心に著しい勢いで増えています。
すでにオフィスとして利用できる状況になっているオフィスビルです。
賃借人は初期費用を大きく削減できるメリットがあり、オーナーは賃借人が見つけやすいというメリットがあります。
セットアップオフィスの場合は、入居時に大きな費用がかからない反面、出て行くときに壁のクロス、床のマットの入れ替えを条件としているところも多いです。
4. オフィスの原状回復費用が『高額請求』される理由と具体的事例
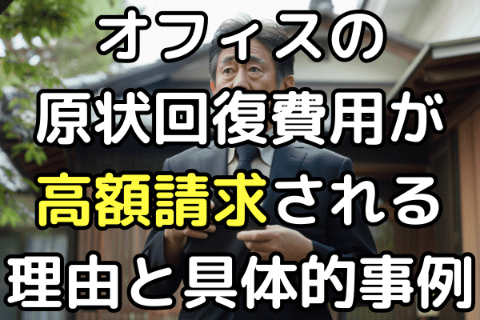
では、なぜ高額な原状回復工事費用が請求されるのか理由と具体例を示します。
原状回復工事費用が高額となる理由は以下の通りです。
- 業者指定で価格競争が働かない
- アップグレードしている
- 通常損耗の回復をしている
各項目について解説します。
1)業者指定で価格競争が働かない
A工事とB工事は、オーナーが指定する業者で工事することになっています。
ですが、工事費用は、賃借人が負担することになります。
オーナーは費用を負担しないため、少しでも安くするというインセンティブが全く働かず、相見積もりなどしてくれません。
オーナーはいつも決まった業者を指定することが多いです。
そうだとすると、その業者はわざわざ値引きする理由はなく、むしろ多めにとってやれという思いがでてもおかしくありません。
具体的事例として、他の業者に依頼していれば500万円程度であるものが、1,000万円と提示を受けたということもザラにあります。
そもそも、建築業界は、孫請けひ孫請けが当たり前の多重構造であり、業者間の価格差はとても大きいです。
それに加えて、価格競争が働かないとなると考えられない金額差になることも稀ではありません。
2)設備のアップグレードまでしようとしている
通常損耗ではなく、賃借人の故意過失による損耗でないばかりか、原状よりもいいものにかえるというアップグレード工事が入っていることがあります。
賃貸借契約書にしっかりと記載された約束であれば仕方ないのですが、そうではありません。
当然ですが、より良いものに変える工事が原状回復のはずはありません。
具体的事例として、細かいものですとクロスのランク(耐熱、防音、遮熱、汚れが落ちやすいなど)がアップしている
3)通常損耗の回復をしている
原則として通常損耗は賃貸人たるオーナー負担です。
賃貸借契約書にしっかりと記載された約束であれば仕方ないのですが、そうではないことがおおいです。
また、アップグレードとまではいかないが、通常損耗を超えた回復をしていることも多いです。
ぱっと見わからないため判断が難しいところです。
5. オフィスの原状回復費用を削減するための4つのチェックポイント
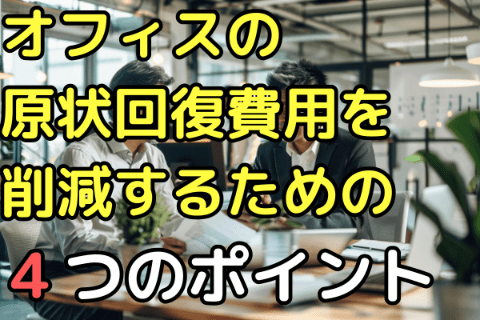
では、どのように原状回復工事費用を削減するのかを解説します。
1)賃貸借契約における原状回復の範囲が適切か
賃貸借契約書の原状回復の範囲を確認してください。
見積もりの工事箇所、その項目が、賃貸借契約書に記載されている原状回復の範囲であるのかをチェックします。
2)経年劣化・通常損耗であるか確認
経年劣化、通常損耗は原則は賃貸人負担です。
ですが、賃貸借契約書において、賃借人負担としているものがあります。
まず、経年劣化、通常損耗の回復が必要であるかを確認してください。
回復が必要だとすると、どの部分の経年劣化、通常損耗が賃借人の範囲となっているかを確認してください。
3)アップグレードしていないか
原状回復の範囲には入っているとしても、工事内容が適切であるかを確認してください。
あくまで借りたときの状態であるので、その時よりもより良いもの、より良い状態にする必要はありません。
原状回復はあくまで修繕であり、改修工事ではないです。
たとえば、断熱材が加わっている、断熱塗料が使われている、バリアフリーにする、手動であったのにセンサー式になるなどです。
4)具体的な工事費用が適切であるか
最後に、具体的な工事費用が適切であるかです。
建築業界はひ孫請けなど多重構造が普通にあり、当然ですが中抜きされて発注されるため、間に多くの業者が介在すればするほど費用がかかることになります。
見積もりにこの業者は二次請けですと書いていないので、外部からは判断ができません。
そのような多重構造とその他営業コストなど様々な要因から、業者によって価格差がかなり大きいのが建築業界です。
2倍、3倍という差が出ることもあります。
しっかり相見積もりをとって、できれば3、4つの業者と比較するのが望ましいです。
6.オフィスの原状回復費用を減額交渉で弁護士ができること
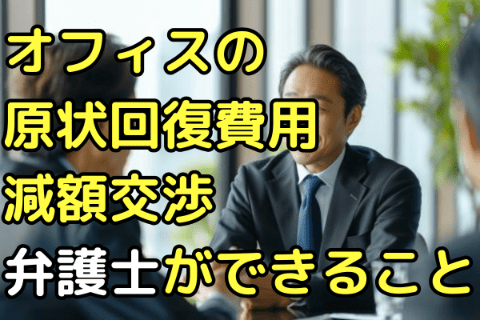
先述した通り、原状回復工事費用を押さえる流れはお示ししました。
ですが、原状回復の範囲から簡単に特定できません。
先述の通り、原状回復の範囲に争いがおきないように詳細に記載されている賃貸借契約書が少ないからです
数行でざっくり書かれていることが多いです。
つまり、原状回復の範囲が明確ではなく、争いうるということです。
弁護士に依頼することで、実務的な観点をとらえつつ、依頼人に有利な解釈をして、原状回復の範囲、アップグレードしていないか、通常損耗を回復させられていないかなど確認して交渉します。
専門的な交渉をしつつも、金額によっては裁判で争いを検討します。
オーナー側としては、早急に解決して次のテナントを入れたいという事情がありますから、そういった状況も踏まえながら、適切な原状回復工事費用にします。
弊所でも、オフィス原状回復費用の値下げのご相談について、実績がございます。
初回相談は無料ですので、まずは1度ご相談ください。
7.そもそも原状回復を必要としない方法
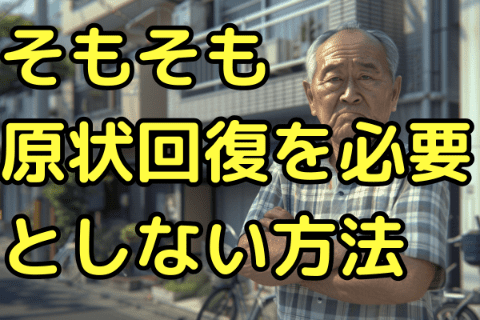
ところで、そもそも原状回復しなくていい方法を探すのも検討してください。
知り合い、友人を中心に、居抜きでそのまま借りてくれる会社を探しましょう。
居抜き専門の仲介業者もあるようです。
借りる側も大きく費用削減できますからありがたい。
居抜きで貸すことは、オーナー側の了承が必要です。
オーナー側も工事期間中のフリーレント期間を短くできるなどメリットがありますし、多くのオーナーが受けてくれるのではないかと思います。
8. 次の物件でオフィスの原状回復費用を抑えるポイント
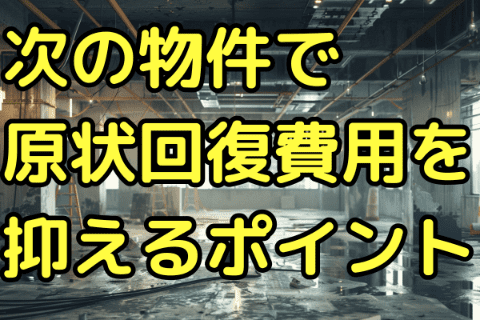
今回の退去で原状回復工事費用が高額だったのを受けて、次に借りる物件でそんなことが起きないようにしましょう。
1)物件選び
初期費用がすくなくてすみ、原状回復の範囲が限定されるセットアップオフィスを借りるのも選択肢です。
昨今、都内では大手デベロッパーもセットアップオフィスに参入しており、選択肢が増えています。
原状回復は必要だが、初期費用を押さえられてトータルで費用を抑えるために、居抜き物件を探すというのも選択肢です。
2)契約書確認
賃貸借契約書を精査しましょう。
オフィスの賃貸借契約書において、見ておくポイントは
- 定借か普通借か
- 早期解約などの違約金
- 原状回復の範囲
などです。
原状回復の範囲が広く書かれている場合は借りる時点で交渉して修正してもらいましょう。
まとめ
オフィスの原状回復工事費用を減額する方法をまとめます。
オフィス退去時の原状回復費用は、多くの場合、大家側が不当に高額な請求をするため、減額できる可能性があります。
そもそも原状回復とは、借主が故意・過失で損耗させた部分を修復するものであり、経年劣化や通常損耗は大家負担が原則です。しかし実際の契約書では曖昧な表現が多く、減額交渉の余地が十分に存在します。
原状回復工事はA・B・C工事に分かれ、特にオーナー指定のB工事では価格競争が働かず、高額請求の原因となっています。また、設備のグレードアップや本来不要な通常損耗の修繕が含まれるケースもあります。
原状回復費用を削減するためのポイントは、
- 契約書上の原状回復範囲の確認
- 通常損耗や経年劣化の費用負担を明確化
- 不要なグレードアップ工事を排除
- 複数業者からの相見積もり取得
の4点です。
専門的知識を持つ弁護士に依頼することで、契約内容を詳細に分析し、適切な交渉が可能になります。また、退去後の原状回復工事自体を回避するため、居抜きで次のテナントを見つける方法も有効です。
次の物件選定では、セットアップオフィスや居抜き物件の検討、契約時に原状回復の範囲を交渉することで、将来的な費用を大幅に抑えることが可能となります。

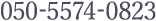

 貸主様向け / 顧問契約
貸主様向け / 顧問契約