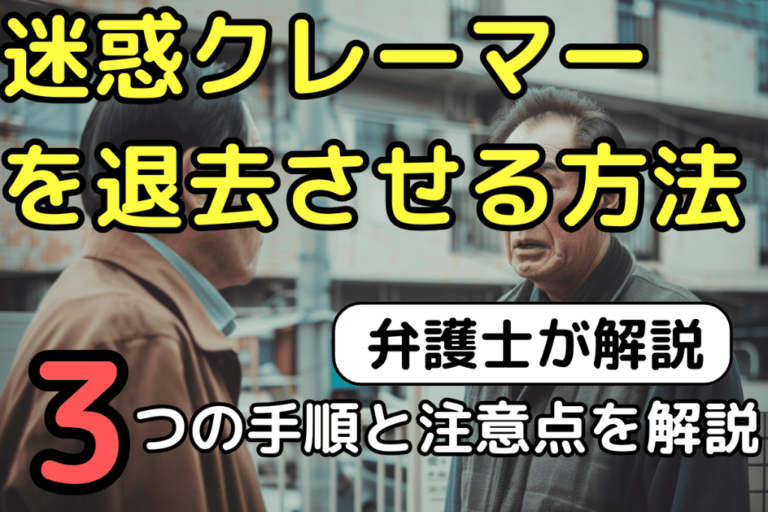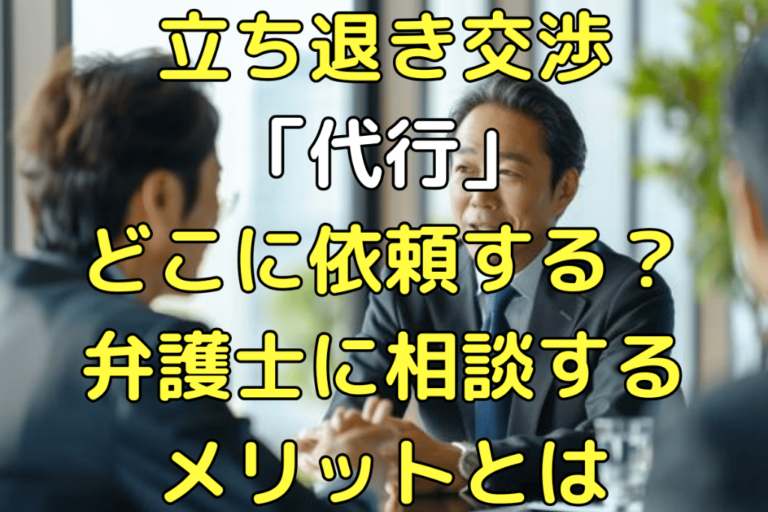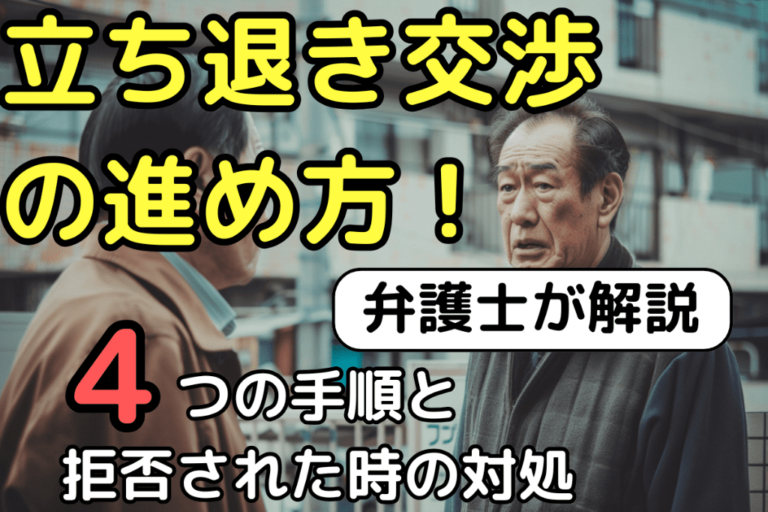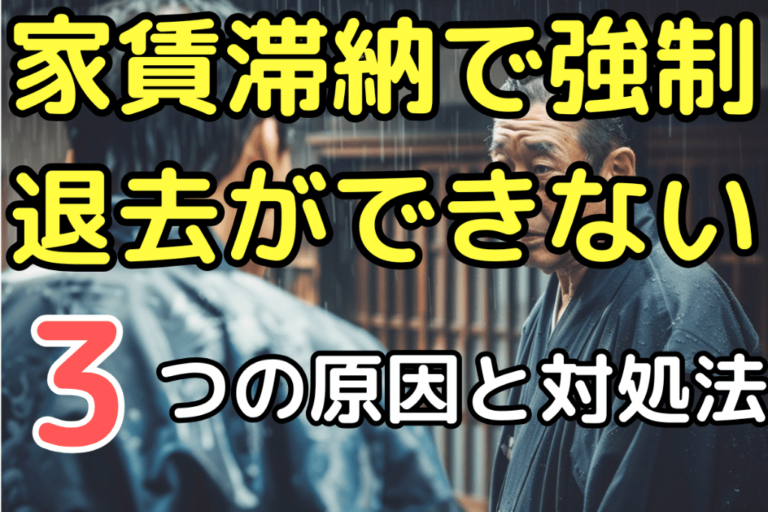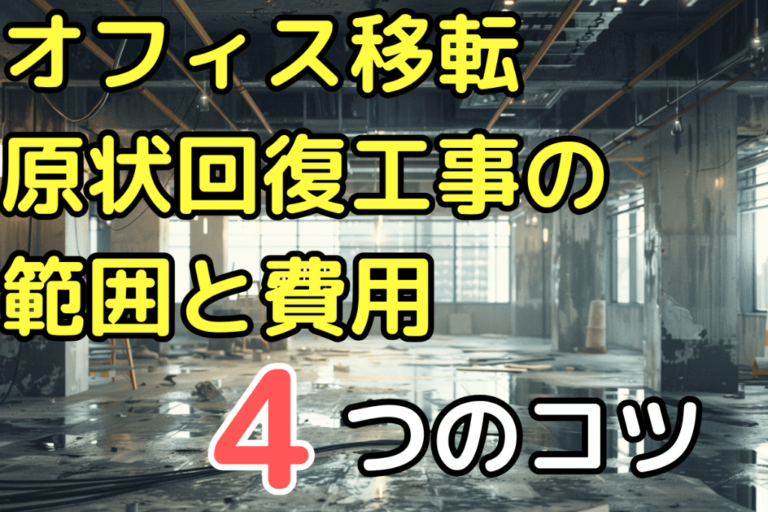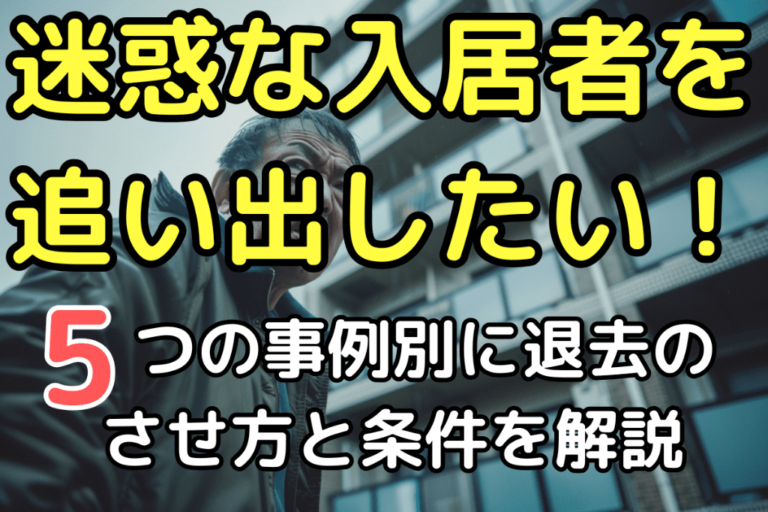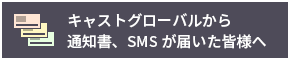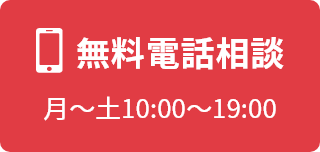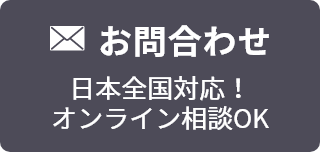- 最終更新:
建物明渡請求・明け渡し訴訟とは?期間と流れ・費用を弁護士が解説!
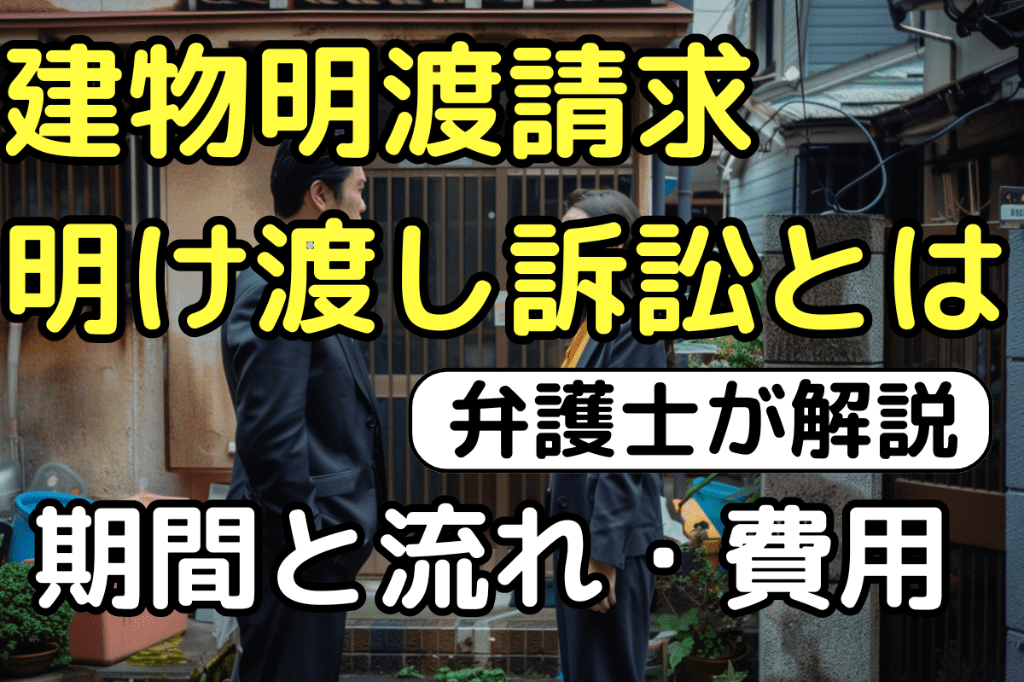
困った入居者がいて出て行ってほしい。
ですが 、交渉が難航しており、明け渡し訴訟も視野に入れて明け渡し請求を考えている。
出来る限り速やかに出ていってほしいですよね。
この記事では、訴訟も視野に入れて明け渡し請求をするための流れを解説します。
【この記事でわかること】
- 明け渡し請求と明け渡し訴訟の流れ
- 迷惑行為などを警告してもやめてくれないとなると明け渡し請求を検討する
- 明け渡し請求から明け渡しを認める判決を得るまで3ヶ月~6ヶ月
- 明け渡しにかかる費用は、実質的には貸主が負担すること
- 明け渡し訴訟にかっても出て行かない場合は強制執行をするしかない
- 明け渡し訴訟を弁護士に任せるメリットは、交渉から強制執行まで任せられ、相手との直接交渉も任せられること
なお、明け渡し請求・訴訟を含めた、「入居者を強制的に立ち退かせる流れ」の全体像は、以下の記事で詳しく解説しています。
「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」
目次
1.「明け渡し請求」と「明け渡し訴訟」とは
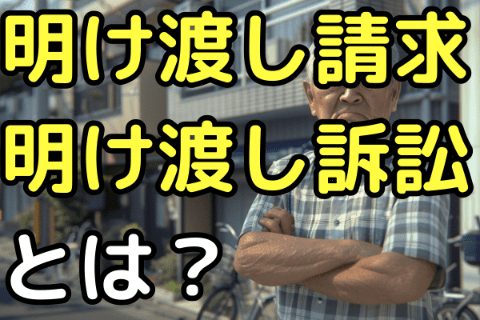
「明け渡し請求」と「明け渡し訴訟」は、どちらも入居者を退去させるためにとる手段です。
ここでは次のように分類します。
明け渡し請求:賃貸借契約の終了を通知すること
┗内容証明郵便で行うのが効果的
┗「明け渡し訴訟」の1歩手前のイメージ
明け渡し訴訟:明渡請求に応じない相手に対し、裁判を通じて明渡しを求める訴訟
┗明け渡し訴訟に勝訴すれば、晴れて法的に強制退去ができる
明け渡し請求は、「建物明渡請求」と表記されたりもします。
入居者を(正当な理由で)退去させたいけど、相手が応じない。
そんな場合に、裁判所の力を借りて正式に「強制退去させて良し」という判決をもらうための、法的手続きだと思ってください。
1)明け渡し請求の前に直接の話し合いをするのが一般的
「明け渡し請求」は、いきなり一方的に通知するものではなく、その前段階として入居者との直接のやり取りが行われるのが一般的です。
例として、以下のようなやり取りが該当します。
- 賃料の滞納がある場合
- →「速やかに家賃を払うように」と催促
- 騒音問題を起こしている場合(迷惑行為)
- →「行動を改善してください」と警告
- 退去してもらいたい事情がある場合
- →「こういう事情で、〇月までに退去してほしい」と要望
上記の通り、「退去してくれ」というやり取り以前に、「問題行動、違反行為をやめるように」というやり取りも含みます。
この段階で入居者が応じることもありますが、話し合いに応じなかったり、そもそも連絡が取れないといったケースでは、内容証明郵便などによる「明け渡し請求」に移行することになります。
2)明け渡し請求・訴訟を検討するべきタイミング
明け渡し請求を検討するタイミングは、明け渡しを求める理由(入居者がやっている違反や迷惑行為の種類)にもよりますが、入居者に警告したにもかかわらず是正されない時点です。
例えば、家賃滞納であれば、家賃滞納があり催促したにもかかわらず、次月分も払われない場合です。
騒音トラブルなどを起こしている場合は、騒音トラブルを注意したにもかかわらず是正する気がないというタイミングが考えどきです。
一方で、明け渡し訴訟は、相手が自主的に出ていってくれそうもないときです。
この時から検討を始めて、裁判を起こす以上勝ちにいく必要がありますから、勝てる確立を最大限高める努力をやり始めなくてはなりません。
いずれのタイミングも弁護士に相談することをお勧めします。
あなたにとってベストを一緒に検討できる専門家となります。
2.明け渡し請求〜明け渡し訴訟までの流れと期間
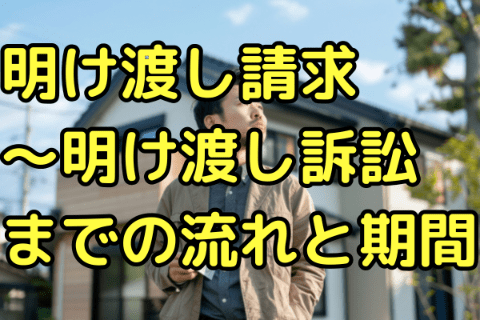
明け渡し請求から明け渡し訴訟までの流れと期間を説明します。
全体として、「明け渡し請求(内容証明の送付)」から「判決の言い渡し」までの期間は、スムーズに進んだ場合でおおよそ3〜6ヶ月程度が目安となります。
相手が欠席したり、全面的な「争わない」姿勢をとれば早期に判決が出ることもありますし、逆に主張の応酬や証人尋問が多くなると半年以上かかることもあります。
以下、それぞれのステップごとの流れと所要期間を詳しく見ていきます。
1)内容証明郵便の送付(明け渡し請求)
内容証明郵便により、賃貸借契約書が終了したので速やかに出ていって欲しい旨を送付します。
内容証明証明郵便とは、お手紙の内容を郵便局が証明してくれるため、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を送ったのかを立証することが容易になる郵便です。
口頭だと言った言わないという話になりますが、内容証明郵便を使うことで言ったことが明確に証拠化できます。
裁判において証拠として使われることがおおいです。
2)契約解除
予告した日、内容証明郵便が到達した日をもって、賃貸借契約を解除します。
ですが、解除が必ずしも有効に確定するということではありません。
こちら側としては賃貸借契約を解除したと考えているということです。
3)裁判所に訴状を提出する
裁判を起こすために、印紙(裁判所に払う費用)をそえて裁判所に訴状などを提出します。
どの裁判所に訴状を提出するかは、不動産がある地域を管轄する裁判所となります。
どの裁判所がどこを管轄しているかは、裁判所の管轄区域表を確認ください。
訴状はどのように記載するものかということは、裁判所のホームページにひな形がありますので、参考にして下さい。
4)第一回期日
裁判所から第一回の期日をいつにするかの連絡が来ます。
訴状等に不備があった場合は、その不備を修正してほしいという連絡が来ます。
第一期日にはこちらは行かなければならないことに注意が必要です。
一方で、相手は行かなくても構いません。
これは、第一期日の日時が相手の確認なく決まるという手続き的な側面があるためです。
5)第二回以降の期日
期日は、両当事者が主張立証を尽くすまで行われます。
ですが、相手が、第一期日までにこちらの主張を全面的に認めた場合、裁判所になんらの連絡なく欠席した場合は、第一期日で審理を終了することがあります。
二回目以降の期日は、相手と日程を合わせます。
電話、オンラインを利用することで、裁判所に出向く必要はありません。
6)証人尋問
審理の終盤には証人尋問があり、当事者、関係者が裁判所に出向いて、言い分を述べる機会があります。
この手続きは、書面などの客観的な証拠を出し尽くして主張立証した後に、それを補完する役割があります。
7)和解
裁判をおこした後であっても、本人と直接交渉して和解することも出来ます。
また、裁判所から和解をするように進められることが何度かあるでしょう。
裁判所が和解を進める理由は、和解するということは両当事者が納得するということになり、紛争を包括的終局的に解決できます。
和解をせず判決を出したとしても、どちらかが納得いかないと控訴することになり、事件の終局的解決ができないからです。
8)判決言い渡し
両当事者が主張立証を尽くして、裁判所に和解をすすめられたが合意できなかった場合に、裁判所が判断を下すという判決になります。
判決に不服がある場合は、判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴することが出来ます。
控訴すると、その地方裁判所を管轄する高等裁判所へ審理がうつることになります。
3.明け渡し訴訟にかかる費用と負担者
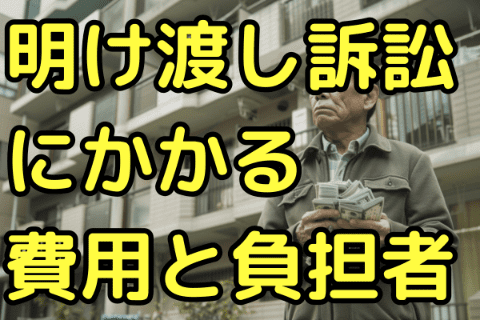
明け渡し訴訟にかかる費用とその負担者は次の通りです。
| 費用 | 金額目安 | 負担者 |
|---|---|---|
| 訴訟の印紙代
裁判所に払う裁判費用 |
50,000円※1,000万円の場合
固定資産税評価額の1/2を基準 |
貸主(原告)※ |
| 訴訟のその他実費 | 1万円程度 | 貸主(原告)※ |
| 弁護士費用 | 30万円~※事案による | 貸主 |
費用は少なくとも50万円はかかります。
そして、納得いかないかもしれませんが、訴訟手続き、弁護士費用含めて費用の負担はすべてこちら側になります。
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)と定められており、勝訴した場合には相手が払うことになります。
ですが、実際に訴訟費用を相手が払うことを期待できず、結果、こちらが負担することになります。
弁護士費用は、裁判の結果に関わらず、依頼した人の負担となります。
4.明け渡し訴訟に勝っても入居者が出ていかない場合の対処
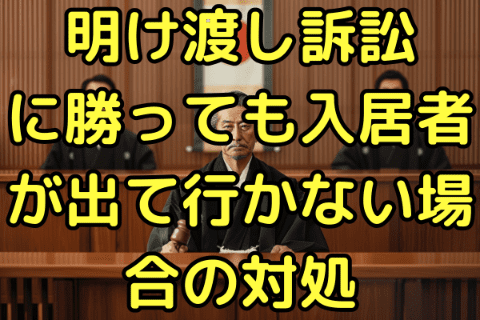
明け渡し訴訟に勝った場合、晴れて入居者の強制退去が法的に認められたことになります。
ですが、中にはそれでも出ていかない入所者もいます。。
この場合には、明け渡しを求める「強制執行」を申立てることになります。
強制執行とは、裁判所が強制的に入居者及び入居者の持ち物を排除して、こちらに引き渡してくれる手続きです。
明け渡し訴訟の判決が確定してから、目安として2週間程度を過ぎても入居者が退去しない場合や、立退きの意思をまったく示さない(無視・居座りなど)場合には、速やかに強制執行の申立てを検討してください。
強制執行の申立ては、確定した判決書などを添付して強制執行申立書等を執行官室に提出します。
不動産の地域を管轄する地方裁判所の執行官室に提出します。
執行官と打ち合わせをして現地に赴き入居者を排除します。
なお、強制執行の断行日までの流れも含めて詳しく知りたい方は、「強制退去・立ち退き強制執行の方法と流れ!条件や期間も弁護士が解説」をご覧ください。
5.明け渡し訴訟を弁護士に相談するメリット

明け渡し請求、訴訟は弁護士に相談するのがおすすめだと述べてきました。
弁護士に相談・依頼するメリットは、次の通りです。
- 5章で解説したあなたにとってのベストタイミングを図りつつ、請求・訴訟をする準備ができる
- 相手との交渉をまるっと依頼できる
- 訴訟手続きについてもまるっと依頼できる
特に、相手との交渉はとても大変で心理的負担はものすごいものがあります。
弁護士に依頼することで、相手と直接接触する必要がなくなり、ストレスがかかりません。
また、裁判手続きにおいては、こちらの主張を立証しなければなりません。
専門の弁護士であれば、どうやったらこちらの主張を裁判所に正しいと思ってもらえるかという観点から立証をします。
まとめ
明け渡し請求から明け渡し訴訟についてをまとめます。
賃貸物件から入居者に出て行ってもらいたいのに、退去に応じない場合、法的な手続きが必要になります。
まず行われるのが「明け渡し請求」です。
これは、直接の話し合いや内容証明郵便を使って退去を求める行為で、「明け渡し訴訟」の一歩手前です。警告しても改善しない場合などに検討します。
請求に応じない相手に対し、裁判所に退去を求める訴訟を起こすのが「明け渡し訴訟」です。
これに勝訴すれば、強制的に退去させることが法的に可能になります。
手続きの主な流れは、内容証明郵便送付後、訴訟提起、複数回の口頭弁論を経て判決となります。
スムーズに進んだ場合でも、内容証明送付から判決までおおよそ3~6ヶ月程度が目安です。
訴訟には印紙代や弁護士費用など、数十万円単位の費用がかかり、多くの場合貸主が負担します。
さらに、訴訟に勝訴しても入居者が自ら退去しない場合は、裁判所に「強制執行」を申し立て、裁判所の執行官に強制的な立ち退きを実行してもらう必要があります。
これらの手続きは専門知識が必要で時間もかかるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
交渉から訴訟、強制執行までサポートしてもらえます。
退去請求について参考になれば幸いです。



 貸主様向け / 顧問契約
貸主様向け / 顧問契約