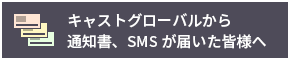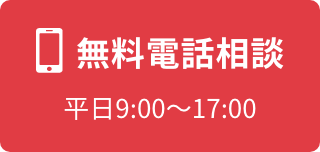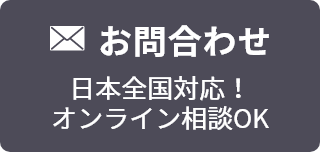緊急事態宣言が解除されてしばらく経ちしましたが、未だに外国人の入国は制限されており、新規の技能実習生の受入れは難しい状況が続いています。
そのような最中、さる6月23日に技能実習に関する行政処分が公表されました。
監理団体については3件の許可取消しと1件の改善命令、実習実施者(受入先企業)については技能実習計画の認定取消が11件です。
2018年7月に現行の技能実習制度となってから最初の行政処分がなされました。それから約2年経過しましたが、その間、数か月ごとに行政処分が公表されています。公表の頻度や1回当たりの処分件数は2019年下半期ころから増加傾向にあります。
今回はコロナの影響で処分の時期が調整されていたためか約4か月ぶりの公表となりましたが、1回あたりに公表された件数としては過去最大となりました。
まず本稿では監理団体に関する処分について述べます。
監理団体の処分理由の分類
許可取消しとなった3件の理由は
①入国後講習を認定計画通り実施しなかった、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出した、実習実施者に対して訪問指導を適切に行っていなかった
②現地送出機関との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の覚書を締結していた
③他人に監理事業を行わせていた
というものでした。
①については、2020年2月にも類似した理由で許可取消しとなった事例がありました。2月の事例では、実施実習者の監査の不実施と入国後講習の不実施が理由として挙げられていましたが、どちらも「監理事業として実施すべきことを怠っていた」ことが問題とされています。
②については、2019年10月にも同様の理由で許可取消しとなった事例がありました。違約金の定めがあることは、労働の強制など技能実習生の重大な人権侵害につながりかねないものであり、技能実習制度における重大なタブーです。
③は、今回が初めてのケースです。いわゆる名義貸しだと思われます。名義貸しは許可制度の潜脱にほかなりませんから発覚すれば重い処分を受けることは当然です。
改善命令となった1件は
- 実施実習者に対する監査を適切に行っていなかった
ことが理由として挙げられています。
技能実習を受け入れる上で注意すべきこと
監理団体としては、違約金の定めや名義貸しをしないことは当然として、「監理事業として実施すべきことを行う」という基本中の基本を守ることが必要不可欠です。
技能実習生を受入れている企業としても、監理団体の業務に注意を払う必要があります。万が一、監理団体が許可取消しとなった場合、監理団体を変更しなければならなくなり、負担を強いられる可能性があります。技能実習生の実習の継続が困難となる可能性も否定できません。
不適切な監理団体を選んでしまうことは、受入先企業にとってもリスクとなり得ることを意識することが必要です。
そもそも、このようなずさんな監理団体を利用することは、技能実習の効果を半減させ、更には技能実習生の人権を侵害しかねません。技能実習生を単なる「安価な労働力」としか見ない企業ならばともかく、技能実習制度を通じて技能実習生と企業双方の健全な発展を目指すのであれば、ずさんな監理団体を利用することは避けなければなりません。