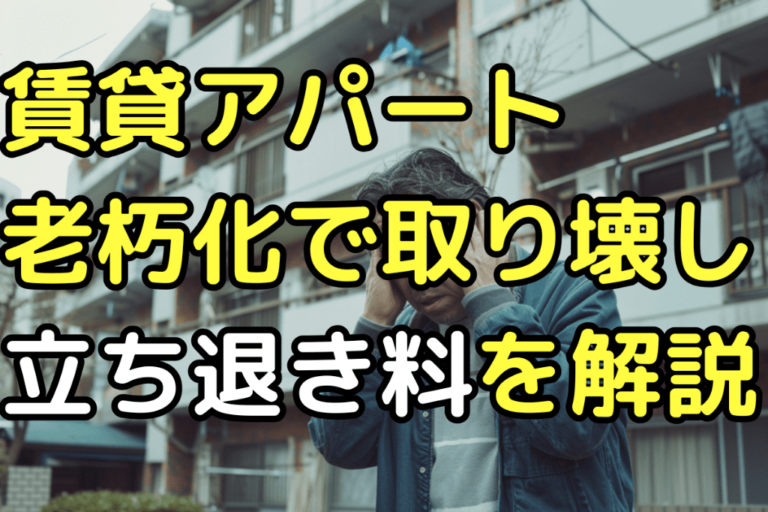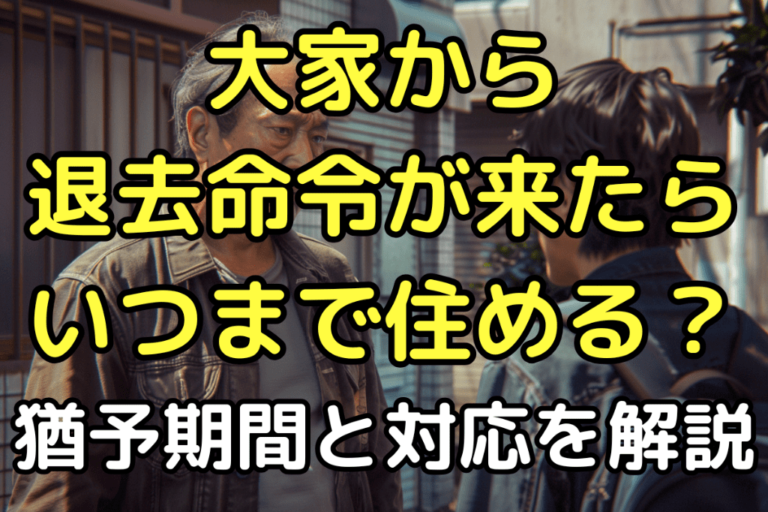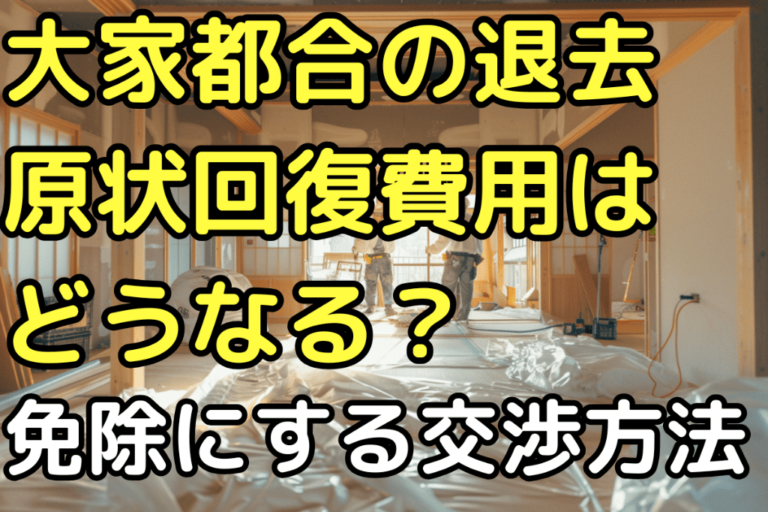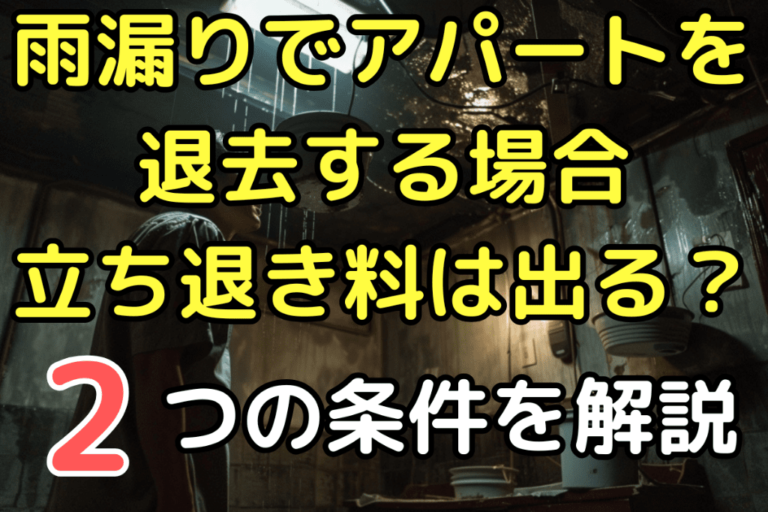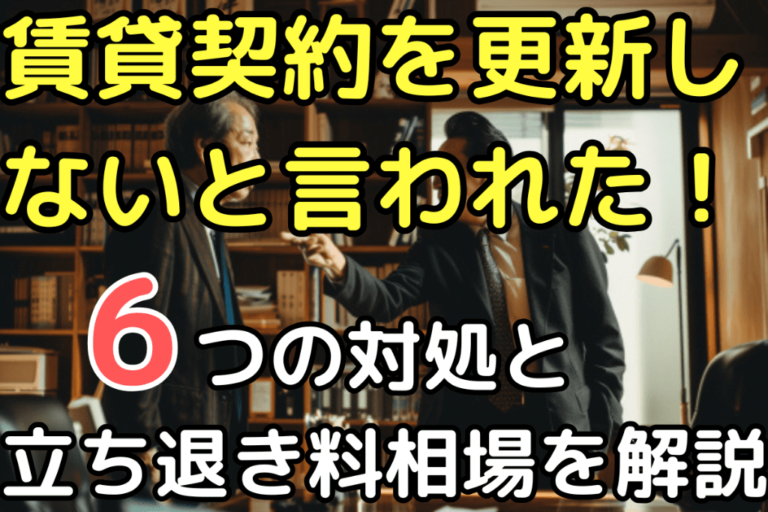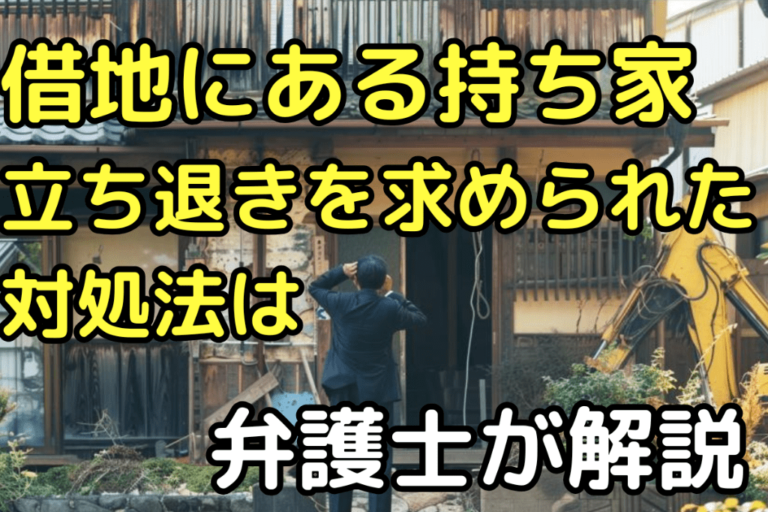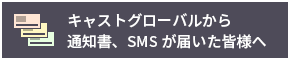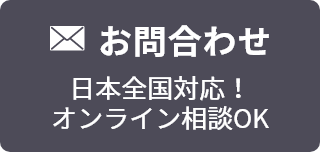- 最終更新:
借地の立ち退き|4つのケース別の立ち退き料相場と交渉方法を解説
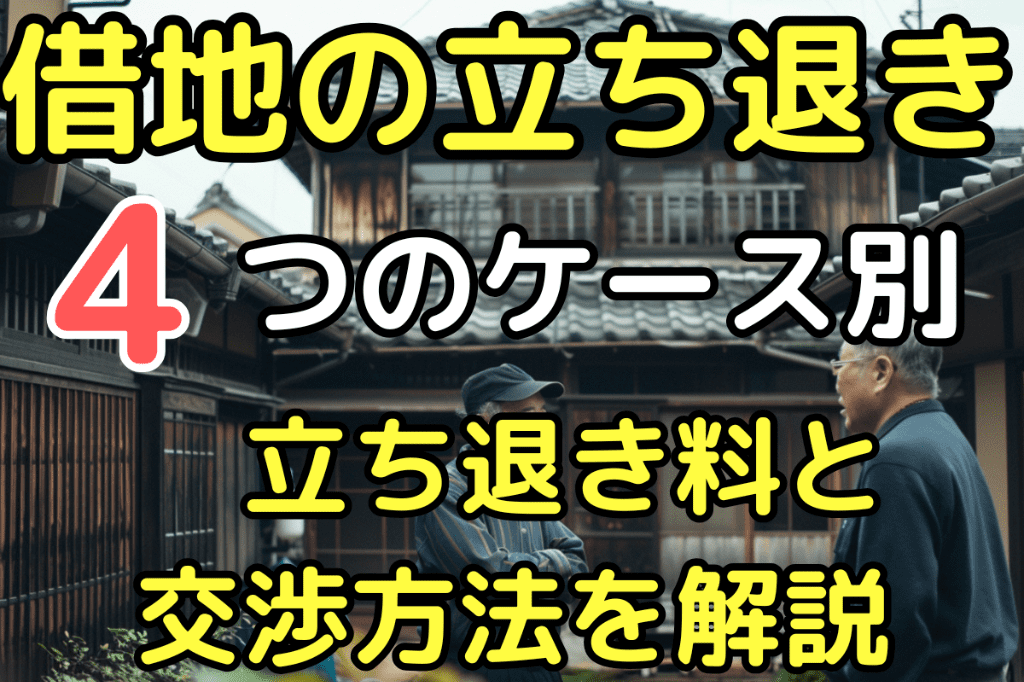
地主から立ち退いて欲しいと言われた。
立ち退かないといけないのか、どういうケースであれば立ち退かなくてよいのか、立ち退くのであれば立ち退き料がほしいなど疑問が多いと思います。
本記事では、借地上に建物を建てて住んでいる借主が、地主に立ち退いて欲しいと言われた場合にどのように対応するのかを解説します。
【この記事でわかること】
- 3つの借地権の立ち退きのルール
- 普通借地権:立ち退き拒否可能で、立ち退きなら立ち退き料もらえる
- 定期借地権:立ち退き拒否不可能で、立ち退き料もらえない
- 旧法借地権:立ち退き拒否可能で、立ち退きなら立ち退き料もらえる
- 立ち退かないといけないかを左右するのは正当事由と立ち退き料
- 立ち退き料に補完されて正当事由が強ければ立ち退かないといけない
- 立ち退き料の内訳は、借地権価格をメインとして、移転費用、建物時価、引越し費用
- 5つのケース別立ち退き料の相場
- 立ち退きを拒否した2つの裁判事例を紹介
- 地主との立ち退き交渉の流れ・手順
- 立ち退き料を増額する4つのポイント
- 地主側の正当事由の強弱を見極める
- あなた側の正当事由を訴える
- いつまでに立ち退いてほしいのかを確認する
- 交渉内容はすべて残す
- 弁護士に相談するメリット
- 立ち退き料の増額が期待できる
- 立ち退き回避ができる可能性が高まる
- 面倒な交渉を丸投げできストレスから解放される
なお、一軒家に限らず立ち退き料の相場全体について知りたい方は、「立ち退き料の相場は?7つのケース毎にいくらもらえるか・内訳を解説」をご覧ください。
目次
1.【3つの借地権】借地の立ち退きについての法的ルール
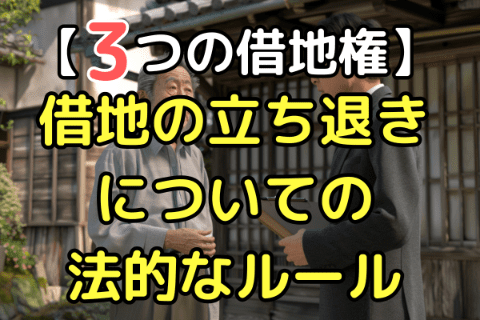
地主から「更新しないので立ち退いてくれ」と言われた場合、どのような契約で土地を借りているかによって、対応の仕方や立ち退き料がもらえるかどうかも変わってきます。
土地の借り方(借地権)の種類は以下の3つになります。
- 普通借地権
- →原則立ち退き拒否可能。立ち退きなら立ち退き料がもらえる
- 定期借地権
- 立ち退き拒否できない。立ち退き料も出ない
- 旧法借地権
- →原則立ち退き拒否可能。立ち退きなら立ち退き料がもらえる
契約書を確認頂き、上記のどれに当てはまっているかをみて、当てはまる借地契約について、ルールを把握しましょう。
定期借地権とは、期間が定まっているということであり、契約期間の終了をもって土地を明け渡す契約です。
普通借地権とは、1992年8月以降に、建物を所有する目的で土地を借りる契約をした場合です。
他方、旧法借地権とは、1992年7月以前に、建物を所有する目的で土地を借りる契約をした場合です。
当初の契約が旧法借地権であれば現在も同じであることが多いです。
普通借地権に切り替えていることも稀にありますが、ほとんど見られません。
1)「普通借地権」だった場合のルール
普通借地権の場合は、基本的に更新が可能であり、半永久的に借りることができるルールになっています。
つまり、原則としてはあなたが「立ち退かなくていい」ルールになっています。
地主があなたを立ち退かせるには、地主側に強い「正当事由」が必要となります。
また、地主に強い正当事由があるにしても、相応の立ち退き料がもらえる(次の章で解説します)。
2)「定期借地権」だった場合のルール
定期借地権に関しては、契約期間内だけの借地契約なので、借主側(あなた)は更新を求めることができません。
つまり、定期借地契約が終了するタイミングで立ち退かなくてはなりません。
持ち家や事業用の施設などがあったとしても、それをを取り壊して更地にして、立ち退かないといけません。
立ち退くのが前提の契約となっていますから、立ち退き料ももらうこともできません。
3)「旧法借地権」だった場合のルール
基本的に、立ち退きについては普通借地権と同じと考えてもらって大丈夫です。
借地借家法になり、存続期間、更新期間などが変更されましたが、立ち退きのルールについては実質的な変更はありません。
したがって、原則として、立ち退く必要はなく、立ち退くとしても立ち退き料がもらえます。
それでは、普通借地権または旧法借地権であった場合の立ち退きのルールを見ていきましょう。
2.立ち退きを左右する2つのポイント「正当事由」と「立ち退き料」
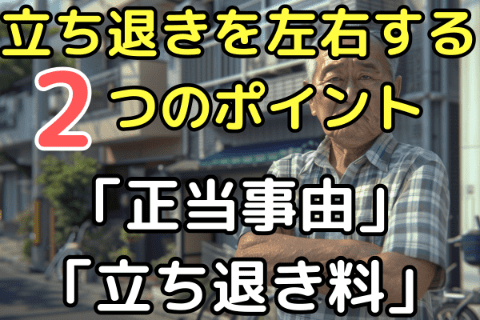
地主から次回の契約終了で更新しないので立ち退いて欲しいと言われても、原則として立ち退かなくていいといいました。
立ち退きを左右するのは、「正当事由」と「立ち退き料」の2つがポイントになります。
1)正当事由とは
正当事由とは、契約を終了することが致し方ないといえる合理的な理由を言います。
土地を借りて家を建てて住んでいる場合に、地主の都合で契約終了してしまうと、借主は不測の損害が生じます。
そこで、借地法及び借地借家法において、借主を保護するために、立ち退いてもらうには正当事由が必要であるとしました。
その正当事由の判断要素は以下のものです。
- 土地の使用を必要とする事情
- 契約に関する従前の経過
- 土地の利用状況
- 財産上の給付の申出(立ち退き料)
これらの事情を総合的に考慮して正当事由を判断することが借地借家法6条に定めてあります。
旧借地法においては、以下のような定めがありまして、正当事由が必要であることが記載されていました。
新法によって、考慮すべき事情が例示された点が変更点になります。
以下、正当事由の具体的な事情がどういうものか、有利不利を解説します。
<参考借地法4条>
借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
①地主側の正当事由
地主側にとって、正当事由(契約を終了することが致し方ないといえる合理的な理由)を判断する事情は以下のようなものです。
- 自らがその土地に住む必要がある
- 家族がその土地に住む必要がある
- 生活費を捻出するために土地を売却する必要がある
- 生活費を捻出するためにアパートを建てて収入を得る必要がある
- 立ち退き料の支払い
これらが正当事由の事情となり、地主側に有利になるものです。
②借地側の正当事由
借地人側にも正当事由はあります。
それはつまり、「契約を終了することが致し方ないといえる合理的な理由」です。
借地人側の正当事由を判断する事情は以下のようなものです。
- 重病の家族がいて、引っ越しすることが相当に困難
- 同等の不動産が近くにない
- 更新料、抵当権設定費用、譲渡承諾料などの定めがあり支払っている
これらが借主側の正当事由の事情となり、借主側に有利になるものです。
逆に、借主側にとって不利になる事情というものもあります。例は以下の通りです。
- 家賃支払い遅れが定期的にある
- 自分は別のところに住んでいて他人に貸している
- 軽微な契約違反がある
2)立ち退き料とは
立ち退き料とは、借主に立ち退いてもらうにあたって支払う費用をいい、正当事由を補完する事情となります。
上で説明した地主側と借主側の双方の事情を考慮して、契約を終了することが致し方ないといえる合理的な理由に足りないとします。
その足りない部分を立ち退き料を支払うことで補います。
正当事由が弱ければ弱いほど、立ち退き料の額が高くなるということです。
また、立ち退きによってかかる費用(引っ越し費用など)の補填という意味合いもあります。
立ち退き料が受け取れることが一般的ですが、問題はその額です。
立ち退き料について詳しく解説します。
3.借地からの立ち退き料の決まり方・内訳
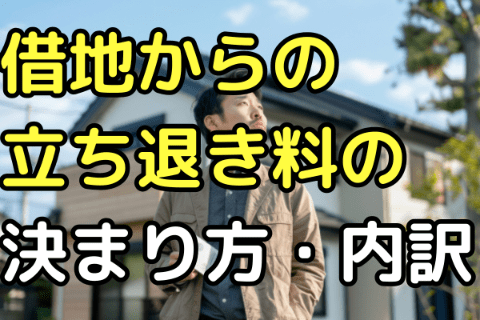
立ち退き料は、次の事情を勘案して決まります。
- 借地権価格
- 移転費用
- (事業用借地の場合)営業補償
- 建物の時価
実質的には借地権という半永久的に借りて住むことができる権利を手放して引っ越すことの対価となります。
1)借地権価格
ずばり借地権価格は、更地価格の6割~8割です。
更地価格とは、その土地に建物が建っていない何もない状態の価格です。
借地権は、半永久的に借りて住むことができる権利として市場で売買されており、価値をもちます。
6割~8割という幅があるのは、地域によって異なっているためであり、基本的には土地の利用価値が高い場所の方が借地権割合が高い傾向にあります。
つまり、地方の栄えていないエリアの土地よりは、都市部の方が高めです。
例えば、東京都中央区日本橋1丁目でしたら、8割となっています。
ご自身でチェックしたい方は、国土交通省の財産評価基準が参考になります。
2)移転費用
引っ越し費用をいいます。
引っ越し業者に支払う費用で家族4名の引っ越しでしたら、20万円ほどでしょうか。
借地権価格と比較すると相対的に大きな費用ではありません。
裁判において積極的に考慮されていない事案も多いです。
ですが、実際にかかる費用ですし、請求しましょう。
3)営業補償(事業を営んでいる場合)
借地上で事業も営んでいる場合です。
例えば、1階を飲食店などの店舗にして、2階、3階を住居としている場合です。
移転に伴って、営業を休止しなければいけない場合には、その間に得られたであろう利益の補償になります。
また、飲食店などの商圏が狭い場合、引っ越しに伴って常連顧客を失ってしまいます。
新天地で営業するにあたり、常連顧客ができる期間の損失を補償してもらいます。
4)建物の時価
その土地の上に建っている建物の価格をいいます。
普通借地権を地主都合で更新しないときは、地主に対して建物を買い取るように請求することができます(借地法4条、借地借家法13条1項)。
契約期間終了でないにもかかわらず立ち退く場合は、条文の根拠はありませんが、本来立ち退く必要がなく立ち退くことになりますから、建物価格も請求しましょう。
木造住宅で30年以上経過していることになりますから、それほど大きな額にならないことが多いです。
例えば、国土交通省の資料によると、22年経過後の木造住宅の価格は1割ほどとなっています。
4.【5つのケース別】借地からの立ち退き料の相場
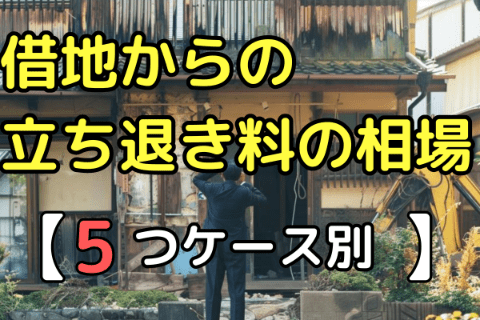
立ち退き料の内訳が分かったところで、ここからは実際立ち退き料はいくらぐらいになるのかを解説します。
といっても一概には言えず、ケースごとに異なるので、本記事では以下の4つのケースにわけて述べていきます。
- 持ち家(一軒家)があり、そこに住んでいる場合
- 持ち家(一軒家)があるが他人に貸している場合
- 住居だけでなく事業をしている場合
- 再開発が理由で立ち退く場合
- 建物が建っていない場合
あなたの借地の状況に当てはまる項目をチェックしてみてください。
1)持ち家(一軒家)があり、そこに住んでいる場合
持ち家(木造2階建)が立っている場合の立ち退き料相場は、1,000万円程度です。
過去の裁判例を確認して示しています。
ですが、東京の都心5区と地方では大きな開きがあるように、場所によって大きく異なりますので注意が必要です。
■判例紹介
事案の概要:東京地方裁判所(令和3年8月6日)
まず、借地権付建物価格は、1,152万円と認定されました。
しかし、地主にはさしたる土地使用の必要性はなかった。
土地の賃借期間は、50年超に及び、権利金や更新料の支払いがあったという事実がなかった。
結果:立ち退き料726万6,000円
コメント:
借主が、長期間土地を借りて更新料等も払っておらず、十分な土地利用を果たせていることなどが考慮されました。
なお、借地に持ち家があり、そこに住んでいる場合の立ち退きについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:借地にある持ち家の立ち退きを求められた時の対処法を弁護士が解説
2)持ち家(一軒家)があるが他人に貸している場合
1)と基本的に同じです。
ですが、借主側が住んでいないとは借主側がその土地を必要とする事情は賃料を得るという経済的理由ということになりますから、正当事由に大きな影響を与えます。
自分で住んでいる場合に比べて借主としての正当事由が弱いことになりますから、立ち退き料も低くなるということです。
■判例紹介
事案の概要:東京地方裁判所(令和5年1月13日)
まず、借地権価格は、2,580万円と認定されました。
しかし、借地人は、ここに住んでおらず、建物を他人に貸していました。
また、土地の賃借期間は、70年間に及び、権利金や更新料の支払いがあったという事実がなかった。
結果:立ち退き料1,500万円
コメント:
借主は、別のところに住みその土地を使用する必要が乏しいこと、長期間土地を借りて更新料等も払っておらず、十分な土地利用を果たせていることがあったため、一定の正当事由が認められました。
そのため、借地権価格からその正当事由が考慮されて大きく下がり、この立ち退き料となりました。
3)住居だけでなく事業をしている場合
住んでいるだけではなくて、空いている場所を利用して事業を営んでいるという場合です。
この場合は、先述のように「営業補填」というものが立ち退き料に加算されます。
営業補償は、営業休止期間中の得られるはずだった利益、移転に伴って常連客を失うことによる損失(得意先損失)になります。
事業者の立ち退き料の相場は、営業補償が大きな額となるところ、事業によって売上利益が全く異なるために、相場として平均化することができません。
弁護士に相談すれば、あなたの事業の利益から、妥当な営業補填、そしてそれを含めた立ち退き料を概算できますので、1度相談して見ると良いでしょう。
3)再開発が理由で立ち退く場合
基本的な立ち退き料の内訳は再開発だとしても同じです。
ですが、地主の土地を使用する必要性は、利益のみに集約され正当事由が弱いと判断されやすいため、高い立ち退き料が受け取れる場合が多いです。
さらに、開発業者は再開発によって利益を得る計画を立てていますから、その利益との関係で許容性があれば、相場とは無関係に高い立ち退き料を払ってくれる可能性があります。
■事例紹介
再開発については裁判ではなく事例を紹介します。
なぜなら再開発の場合は裁判ではなく話し合いによる解決の方が高い立ち退き料を得られることが多いからです。
借地権価格が4,000万円程度でしたが、立ち退き料が1億円以上となった事案などがあります。
なお、再開発の立ち退き料については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:再開発による立ち退き料の相場は?店舗・一軒家別に増額方法も解説!
4)建物が建っていない場合
借地に建物が立っていない場合は、立ち退き料はもらえません。
例えば、ソーラー発電や駐車場として借地を活用していた場合です。
建物が建っていない場合は、旧借地法、借地借家法の適用はありません。
旧借地法、借地借家法は、建物所有目的での借地の場合の定めだからです(旧借地法1条、借地借家法1条)。
そのため正当事由がそもそも問題とならず、立ち退き料はもらえないのです。
5.借地からの立ち退きを拒否することはできる?
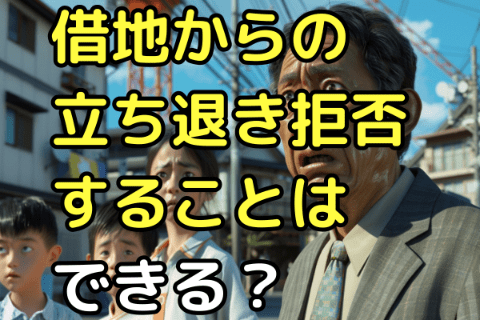
原則として借地契約は更新できるといいましたが、立ち退き拒否が必ずできるわけではありません。
地主側がその土地を利用する必要性が低い(正当事由が弱い)一方で、借地人側が借地を利用しなければ困窮が予想されるようなケースでは、立ち退きを拒否できます。
ただし、地主が立ち退き料をしっかり払う姿勢である場合は立ち退きを拒否することは難しいです。
この場合は、7章で説明しますが、立ち退き料を最大化することを目的とするのが良いでしょう。
とはいえ裁判において立ち退きを拒否した事例ももちろんありますので、一部を紹介します。
1)事例①:事案の概要:東京地方裁判所(令和5年8月3日)
築40年の木造建物に親子3名で住んでいて、親は高齢で年金のみが収入であった。
借地権価格は、2,099万円~2,393万円だった。
地主は、本マンションは法令違反があること、老朽化が進んでいること、一時3ケ月分の地代を滞納したとして、マンションを建築する開発を計画し立ち退き料1,500万円を支払うとして立ち退きを求めた。
結果:
借主は高齢で収入も少なく、他の同居人の収入も少なく、転居が困難であること。
立ち退き料1,500万円を提示しているが、借主の土地使用の必要性を補うだけの金額に足らないとして、正当事由があるということはできない。
したがって、立ち退く必要はない。
コメント:
借主は、資力に乏しく高齢であったことで建物を使用する必要があるとされました。
立ち退き料は、それらを補填するには足りないということです。
2)事例②:事案の概要:東京地方裁判所(令和4年6月28日)
築60年の木造鉄骨造2階建で借主は住居として利用しつつ、1階で居酒屋を営んでいた。
地主は立ち退き料8,837万9,000円を支払うとして立ち退きを求めた。
結果:
借主はそこに住んで居酒屋を営んでおり、生活の糧も得ていた。
一方、地主にその土地を使う必要性がほとんどないことから、相応の立ち退き料を提示したとしても、正当事由を補完できるものではなく、立ち退く必要はないとした。
コメント:
地主側の土地使用の必要性が乏しく、借地人に土地使用の必要性が高ければ、いくら立ち退き料が高額であっても認められないとした事案です。
私の個人的な見解にはなりますが、立ち退き料が足りないということはあっても、いくら高額でも認められないという結論は適切とは思えません。
6.地主との交渉の手順・流れ|準備〜立ち退きまで
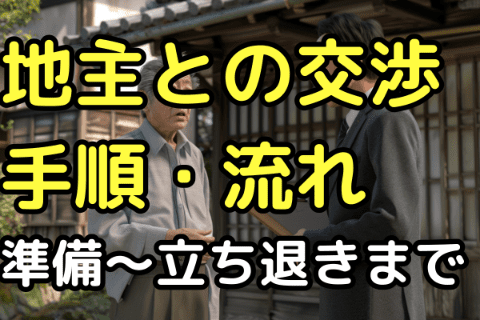
では、地主から契約を更新しないといわれた場合に、どのような手順・流れとなるのかを解説します。
1)あなたの契約状況を確認する
普通借地権なのか定期借地権なのか、契約期間はいつまでなのか、今が切れるタイミングなのかを確認します。
また、このタイミングで契約書を見直して、契約書に記載されている義務違反がないか確認しましょう。
気付かないうちに地主さんに了解を得ていない家族を呼び寄せていた、改築をしていたということがあります。
2)どうしたいのか方向性を決める
立ち退きを拒否するか、立ち退き料を最大化しつつ立ち退きに応じるのか、いずれの方向で行くのかを決めましょう。
どちらか一方に決めず、立ち退きを拒否するが、これぐらいの立ち退き料をもらえるのであれば立ち退いてもいいというのもありです。
3)必要に応じて弁護士に相談する
契約の確認やどの方向性でいくのがいいのかなど判断が難しいという場合に、弁護士 からアドバイスをもらうと有用です。
初回相談無料という事務所を利用して相談すると費用も抑えられます。
当事務所も初回相談無料としていますので、安心してご相談ください。
4)地主と話し合い、交渉を開始する
決めた方向性をゴールにして、地主と交渉を開始します。
これまで解説してきたところを意識しながら、ゴールを勝ち取ってください。
5)地主と合意する(合意に至らなかったら7)へ)
地主と交渉して合意できた場合には合意書を締結してください。
特に立ち退き料を受け取って立ち退く場合は合意書を必ず取り交わしてください。
立ち退かずに契約を更新する場合は、合意書を必ずしも取り交わす必要はありません。
6)立ち退き回避または立ち退いて立ち退き料を受け取る
地主との合意内容に基づき、立ち退きを回避するか、立ち退いて立ち退き料を受け取ります。
7)地主から訴訟提起または地主が諦めて契約更新
残念ながら地主と合意できなかった場合です。
この場合は、地主としては、あなたにどうしても立ち退いてもらいたいのであれば訴訟・調停を申し立てます。
地主が費用対効果などを考慮して立ち退きを諦めるということもあります。
ですが、借地権を更新すると次の更新時期まで立ち退きをできなくなり、その期間は10年以上となります。
10年も待てないとなれば訴訟をしてくるでしょう。
7.借地人向け|立ち退き料を増額する4つのポイント
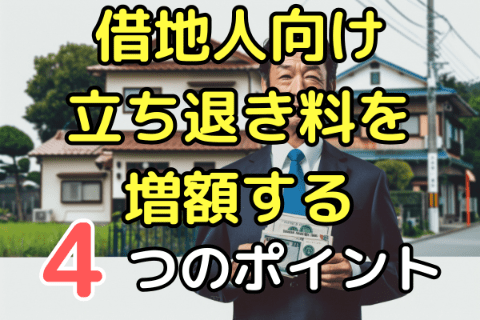
立ち退きをする方向で方針を決めた場合に、立ち退き料を最大化することが目標となります。
1)地主側の正当事由の強弱を見極める
地主の事情、あなたの事情をしっかり分析しましょう。
どれくらい地主にその土地を使用する必要性があるのか、あなたにその土地を使用する必要性があるのかなどです。
相手の事情が弱いことをしっかり伝えることで、立ち退き料を引き上げられる可能性があります。
2)いつまでに立ち退いてほしいのかを確認する
地主があなたにいつまでに立ち退いて欲しいのかを確認しましょう。
契約終了前に立ち退くことで、地主にメリットが大きいのであればそれもカードに使いましょう。
相手の希望に沿って立ち退きをする代わりに、立ち退き料を引き上げてもらいます。
相手にとってその期日が重要であればあるほど、立ち退き料を引き上げてくれる可能性があります。
3)あなた側の正当事由を訴える
1)の逆で、あなた側の正当事由が強いことを訴えます。
あなたが土地を使用する必要性を示します。
例えば以下のような正当事由は大きな効力があります。
- 高齢だったり疾病があったり(または同居人にそういった人がいる)で引っ越しが難しい
- 近くのエリアで代替物件(同じような土地や家)を見つけるのが難しい
- 事業で常連客もいるので、移転すると今まで通りの営業利益が見込めなくなる
あなた側の正当事由が強くなればなるほど、立ち退き料を上げざるを得なくなるからです。
4)交渉内容はすべて残す
交渉内容は、録音できなくてもメモでもいいので残しておきましょう。
メモをとる場合は、交渉直後に取ってください。
言った言わないの不毛な議論をしたくありません。
また、交渉経緯を残すことで、裁判等になった時の証拠になります。
8.借地からの立ち退き交渉で弁護士に相談するメリット
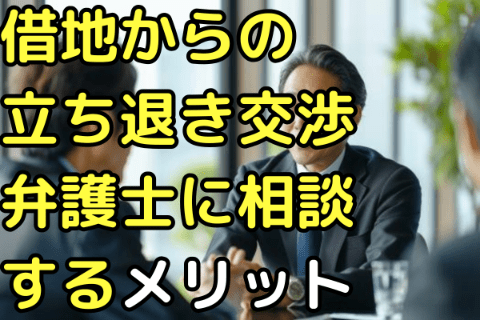
借地からの立ち退きを求められたら、弁護士への相談をぜひご検討ください。
弁護士であれば「どうしても立ち退きたくない(拒否)」でも「最大限の立ち退き料をもらいたい」でも、どんなニーズにも応えて、地主と交渉ができます。
そこで最後に、弁護士に相談するメリットを3つ紹介していきます。
1)立ち退き料の増額が期待できる
大きなメリットが立ち退き料を増額できる可能性があることです。
これまで解説したとおり、立ち退き料の判断は専門的です。
かつ計算で出てくる数字にとらわれずに地主の事情を勘案して交渉で立ち退き料を引き出すことが大切です。
専門の弁護士であれば、適切な立ち退き料を計算しつつも相手の地主の事情を調査して増額を引き出します。
立ち退き料が数倍になるということもあるぐらい、立ち退き料は様々な要因から増減します。
どうせ立ち退かなければならないなら、少しでも立ち退き料を多くもらいたいものです!
2)立ち退き回避ができる可能性が高まる
地主は強い正当事由があることを主張して、立ち退きを要求してきます。
正当事由に対する適切な反論には、専門的な知見、経験が必要です。
不動産の立ち退きに強い弁護士なら、地主の正当事由が強くないことを適切に主張します。
これによって地主の正当事由を適切に評価して、立ち退き回避につながります。
3)面倒な交渉を丸投げできストレスから解放される
弁護士に依頼すれば、立ち退き拒否、立ち退き料の増額交渉だけでなく、立ち退くまで一連の面倒なやりとりをすべて任せられます。
例えば、立ち退きに関する合意書の作成から立ち退き時期、立ち退き料の受け取り、あらゆる地主とのやりとりまで。
これらは、とてもストレスがかかります。
弁護士に任せることで、そのストレスから解放されます。
まとめ
借地に家を建てて住んでいる人が地主から立ち退きを求められた場合の対応、手順をまとめます。
まず、契約書を確認して、普通借地権か定期借地権か、契約終了がいつかを確認しましょう。
定期借地権であったら諦めて立ち退く準備をしてください。
普通借地権であれば、立ち退かないで済む可能性があります。
ですが、納得する立ち退き料をもらって立ち退くというのも検討の余地があります。
あなたのライフプランを見直して、将来設計をしましょう。
立ち退きたくないとなれば、地主とあなたの正当事由を確認しましょう。
正当事由が強いかもしれない、地主が何としても出て行って欲しいという状況であるとなれば、立ち退き料を最大化することを目指す方が良いです。
交渉から立ち退きまたは立ち退き回避まで専門的知識とストレスのかかる交渉があります。
立ち退きに強い弁護士に依頼することで一連を任せることができますし、立ち退き回避、立ち退き料の増額が見込めます。
ぜひ、本記事を参考にして、立ち退き問題を納得して解決してください。

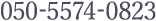

 借主様向け
借主様向け