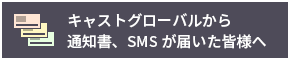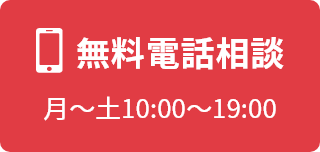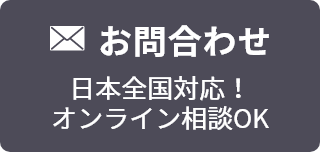団体交渉の対策
団体交渉(立会い)

団体交渉の申し入れがあった場合の対処法
そこで、今回は団体交渉を申し入れられた場合の対処法について解説します。
団体交渉とは?何を話し合う?拒否はできる?
まずは、労働組合の団体交渉の概要を確認しておきましょう。
団体交渉とは
団体交渉とは、労働組合の代表者と企業側が労働条件等を交渉することをいいます。労働者は、憲法によって団体交渉を行う「団体交渉権」が認められており、企業側はそれに応じる義務があるとされています。団体交渉では、以下のような項目が話し合われることが多いです。
- ●未払い残業代問題
- ●ボーナスの査定問題
- ●未払い賃金問題
- ●いじめ問題
- ●不当解雇問題
- ●各種ハラスメント問題
- ●退職勧奨問題
日本国憲法第28条では、従業員が企業と対等な立場で自身の正当な権利を主張できるよう、「団体交渉権」を保障しています。
一般的に団体交渉が行われる場合は、労働組合から企業宛てに団体交渉申入書が届きます。労働組合から団体交渉を求められたら、原則として企業は拒否することができません。正当な理由なく拒否することは「不当労働行為」と呼ばれ、労働組合法で禁じられています。単に拒否するだけでなく、交渉への対応が不誠実な場合も不当労働行為の対象となるため、労働組合との合意を目指した真摯な対応が求められます。
そのほか、以下のような行為も不当労働行為だと判断されますので、注意が必要です。
- 労働組合への加入や正当な労働組合活動などを理由に、解雇、降格、給料の引下げ、嫌がらせ等の不利益取扱いをすること。(ただし、一定の場合に、いわゆるユニオン・ショップ協定またはクローズド・ショップ協定を締結することは妨げられません。)
- 労働組合の結成や運営に対して支配・介入したり、組合運営の経費について経理上の援助をすること。(ただし、従業員が労働時間中に、時間や賃金を失わず使用者と協議・交渉することや、使用者が福利その他の基金に対する寄付をすること、使用者が労働組合に最小限の広さの事務所を供与することは除きます。)
- 従業員が労働委員会に救済を申し立てたり、労働委員会に関する手続において行った発言や証拠提出を理由に、不利益取扱いをすること。
不当労働行為を行った場合、労働組合が労働委員会に対して救済を申し立てることがあります。申し立ての内容に対し、労働委員会が不当労働行為に該当すると判断を下した場合は、企業に救済命令が出されます。救済命令に違反した企業には50万円以下の過料が科せられてしまうため、注意が必要です。
また、従業員から「違法な権利侵害にあたる」と主張され、損害賠償を請求されることも考えられます。こうした不当労働行為に対する制裁は、多かれ少なかれ企業経営に影響を与えることが予想されます。したがって団体交渉には誠実な態度で臨み、救済命令が確定した場合には命令に従うことが大切です。
団体交渉は原則として拒否することはできない
労働組合による、団体交渉は企業側が拒否することはできません。期日を調整することはできますが、正当な理由無く拒否することは「不当労働行為」に該当し、さらなる糾弾を受けることになります。また、意味も無く期日を先延ばしにする行為も、不当労働行為に該当する可能性が高いため、誠実に速やかに対応するようにしましょう。
不当労働行為救済申立てを行わずに、街宣活動を行われた場合は、企業イメージへの影響が甚大です。
したがって、労働組合から団体交渉の申入書が届いたら、速やかに内容を確認した上で、回答する必要があります。
団体交渉に臨む際の注意点
では、団体交渉の際はどのような点に注意すればよいのでしょうか。団体交渉での注意点を解説します。
団体交渉は時間を設定しておき業務時間外とする
労働組合は、団体交渉で要求が認められない場合に、時間を引き延ばそうとすることがありますので、最初から1時間半から2時間程度と開催時間を設定しておきましょう。
また、団体交渉の時間は就業時間外が望ましいです。勤務時間内に行われる団体交渉は、勤務時間ではないため、給与を支払う必要はありません。しかし、給与を支払わないことで新たなトラブルが発生することがあるため、元々給与の支払いが発生しない業務時間外に開催するのが無難です。
開催場所は社外の会議室等が望ましい
団体交渉の開催場所は、どこでも構いませんがトラブルを回避するためには、社外の貸し会議室等が望ましいです。会社側の弁護士事務所でもよいでしょう。
組合の事務所は、組合側の参加人数が増加してしまうおそれがありますし、自社内の会議室では他の従業員や来客への影響が心配されます。
組合が指定する出席者を出席させる必要は無い
労働組合は、社長を出席されるようにと指定することがありますが、従う必要はありません。社長ではなく、協議事項を把握している人事部長や上司などが参加すれば問題ありません。できれば、弁護士にも同席を依頼しましょう。
団体交渉は録音しておく
団体交渉でのやりとりはICレコーダーなどで録音しておきましょう。開始前に、録音することを伝えた上で机上にレコーダーを置いておくと安心です。労働組合側に、不適切な発言等があった場合には重要な証拠となります。
安易に交渉を打ち切らない
労働組合の要求が不当な場合は、交渉が平行線になり行き詰まることになります。しかし、行き詰まったからと言って企業側から交渉を打ち切ることは得策とは言えません。企業側が打ち切ったことで、不誠実団交として不当労働行為を主張されるおそれがあります。また、街宣活動などの過激な活動を行われる可能性があり危険です。交渉を打ち切る場合は、正当な打ち切りであることを労働組合側に書面で示しておくことが求められます。
団体交渉中の配置換えや待遇の変更は慎重に
労働組合による団体交渉が開催されている場合、交渉中の従業員の待遇の変更には細心の注意が必要です。なぜならば、団体交渉への参加や労働組合活動などを理由に、減給したり、左遷したりするような従業員に対して不利益となる行為は、「不当労働行為」として禁止されているからです。全く関係ないことで、配置転換を行ったとしても団体交渉中は「不当労働行為だ!」と主張されかねず、新たな火種となります。
開示する情報をしない情報を取捨選択する
団体交渉においては、労働組合側が経営に関する資料の開示を求めることがあります。企業側は誠実に対応しなければなりませんが、重要な機密事項に該当する資料については開示する必要はありません。組合側から資料の開示が求められたら、開示すべきかどうかの判断に迷うと思いますので、企業法務を専門とする弁護士にご相談ください。
労働組合の暴言や暴力には毅然と対応する
団体交渉中に、労働組合側が暴言や暴力に及んだ場合は、直ちに辞めるように告げ、それでも辞めなければ交渉の打ち切りを検討しましょう。ただし、不当労働行為であると主張されないために、暴言や暴力の証拠である録音を確保しておくこと、書面に残しておくことを徹底しておいてください。
団体交渉を申し入れられたらやるべきこと
次に団体交渉を申し入れられた際に、企業がやるべきことを解説します。
弁護士に団体交渉への立ち会いを求める
団体交渉での企業の発言は、すべて組合側に録音されており不適切な発言をすると、それを逆手にとってさらに紛争が悪化してしまいます。また、不当労働行為に該当する言動をしてしまうと、街宣活動や救済申立てなどの手段を講じられてしまい、企業にとっては不利益となります。
団体交渉では、法的な知識を基にした慎重な立ち回りが求められますので、自社内だけで解決しようとせずに弁護士に立ち会いを求めてください。
弁護士であれば、労働組合と適切に交渉が可能ですので、団体行動によって会社側は不利益を被るリスクを大幅に軽減可能です。
議事録を作成する
団体交渉の際は、書面による議事録も作成しておきましょう。紛争に発展した場合に、どのようなやりとりが行われたかを証明する証拠となり得ます。労働組合側も議事録を作成しますが、その議事録に署名捺印を求められても拒否してください。労働組合側に都合がいい内容が記載されており、確認せずに署名捺印すると不利な状況に陥ることがあります。
団体交渉(立会い)のまとめ
労働組合から団体交渉を申し入れられたら、企業は原則として拒否することはできません。拒否すると不当労働行為を主張されるおそれがあります。また、団体交渉中の対応を誤ると、過激な街宣活動などに発展して、紛争が激化し、企業の経営活動に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、労働組合から団体交渉を申し入れられた場合は、拒否せずに対応し、交渉中は弁護士などの専門家の立ち会いを求めることが重要です。団体交渉では、労働者側の主張を全面的に受け入れる必要はありませんが、受け入れない場合には正当な証拠が必要となります。
労働組合から団体交渉の申入書が届いたら、すぐさま内容を確認して企業法務を専門とする弁護士にご相談ください。回答書の作成や、団体交渉への立ち会いなどを行い、団体交渉に対して適切かつ迅速に対応いたします。